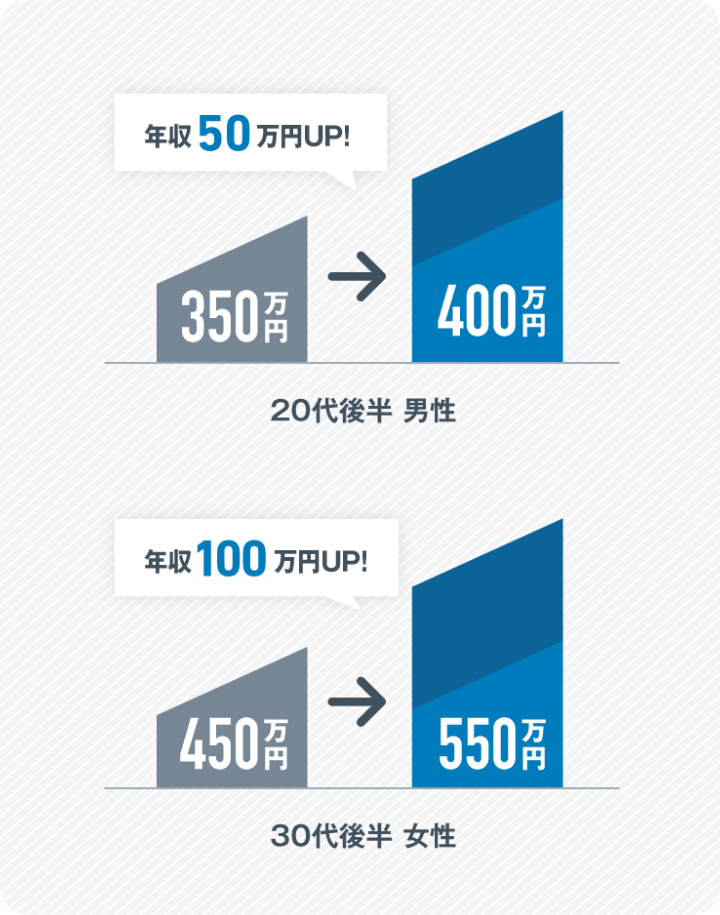ハローワークでは、就職や転職を希望する障害者の方向けに、相談員が職業相談や紹介、職業適応指導、求職者と求人企業が一堂に会する就職面接会などを行なってくれます。
また、障害者向けの求人はもちろん、仕事の内容によっては健常者向けの求人にも応募できる場合もあります。
このように、障害者の仕事探しといっても特別な方法があるわけではなく、健常者の転職活動、就職活動と同じような形で行なうことになるのが一般的です。
この記事では、障害のある人向けに、ハローワークによる支援の詳細や、扱っている求人内容などについて詳しく解説します。
【関連記事】
転職にハローワークは使えない?ハロワのメリットと最大限活用する方法
ハローワークによる障害者支援とは
ハローワークは、実は障害者の就職のための各種支援を行なっています。障害者向けの求人を数多く取り扱っていたり、合同面接会を行なっていたりする他、各企業に対して障害者を雇うことの啓蒙活動を行なったり、求職者である障害者に対して公共職業訓練を斡旋していたりもします。
また、障害に関する専門知識を持った職員が就職に向けた相談や書類の書き方、面接対策はもちろん、求職者の希望をしっかりと企業側に伝えてくれ、必要に応じて面接にも同行してくれるケースもあるそうです。
障害者の中には、就労支援だけではなく生活支援が必要となるケースもあります。
ハローワークは、地域の福祉関係の組織とのつながりもあるため、障害者就業・生活支援センター(就労と生活の両方のサポートを行なう機関)の紹介などを行なう場合もあります。
もちろん、就職が初めての人も利用できますし、就職した後も担当職員が企業と連絡を取り続けるなどのアフターサポートも継続的に行なうので、安心して利用できるのがハローワークの特徴です。
ハローワークは公的機関なので、これらの支援を全て無料で受けられるのもありがたいポイントです。
ハローワークで扱っている主な障害者向け求人
障害のタイプによってできる仕事には違いがありますが、障害者が行なう仕事の内容としては下記が多くなっているようです。
- 事務職
- 工場などの製造関連の仕事
- 作業職
- 運搬
- 清掃
- 包装
- サービス職
ただし、障害者と一言でいってもその障害のタイプはさまざま。
大きく分けると、『身体障害』『精神障害』『知的障害』の3つに分かれますので、この点には注意しなければいけません。
また、同じ身体障害でも、視覚障害、聴覚障害、肢体障害などの違いもあります。
ちなみに、視覚障害者はあんま・マッサージ・はり・きゅう関連の仕事が多く、聴覚障害者では生産工程や労務関連の仕事が多くなっています。
一方で、肢体障害に関しては特定の職種が多くなるといったことはありません。また、知的障害の場合は、作業工程を決めることで障害者が働きやすい環境を作れる製造業が多くなっています。
このように、障害者が就く仕事を見てみると、各障害によって違いがあることが分かります。
【参考: 障害者白書】
障害者がハローワーク以外で仕事を探す方法

障害のある人が仕事を探すにはどうすればいいのでしょうか? 健常者が行なう就職活動の流れとは違うのでしょうか? ここでは、ハローワーク以外の探し方についてご紹介します。
転職サイトで探す
健常者が転職を行なう際には、人材サービス会社などが運営する転職サイトを利用するのが一般的です。
障害者に関しても、仕事探しの手段の1つとして転職サイトを利用することができます。障害者の求人に特化した転職サイトもあるので、健常者と同じように仕事探しをすることも可能です。
ちなみに、障害者用の転職サイトである『at GP転職』を調べてみたところ、2021年4月12日現在で900件以上の求人がありました。
この中にはメガバンクの一般職や大手企業のグループ会社、事務職やエンジニア職などさまざまな会社、幅広い職種の求人を見つけることができました。
障害の内容による部分もありますが、仕事探しの際に転職サイトを活用することは有益だと言えます。
【関連記事】
転職エージェントを利用するメリットとデメリットの全知識
人材紹介会社で探す
障害者を対象とした人材紹介を行なう会社もあるので、そういったサービスを利用するのも1つの方法です。
サービスのおおまかな内容としては健常者のものと変わりなく、サービス利用者の希望条件などを確認した上で、会社が求人を紹介してくれる形です。
求人の紹介だけでなく、面接対策や就職相談、提出書類の添削といったサポートも行なってくれるなど充実の支援体制を整えています。
転職活動が初めてで不安という人は、面と向かって話しながら進めることができる人材紹介会社を利用するのもよいのではないでしょうか。
障害者が就職・転職するにあたり障害をオープンにすべきか
障害者の方にとって、障害をオープンにするかどうかは働く上での大きな問題となります。それは、
- 障害に偏見を持つ人もおり『障害者』という目で見られることになる
- 障害者の求人は一般の求人に比べて少ない
- 仕事内容が限られてしまう
といったデメリットがあるためです。
こういった部分があるのであれば、もしかしたら障害を隠して就職活動をしようと考える人もいるかもしれません。しかし、万が一のことを考えると、障害を隠すことはリスクにもなります。それは、
- 障害を隠し続けなければいけない
- 通院や服薬の際も周囲にバレないように配慮しないといけない
- 障害のために苦手な仕事があっても伝えることができない
- 障害に対する支援制度が利用できない
といったデメリットがあるためです。
障害の影響で体調を崩すこともあるかもしれませんし、通院のために休みを取る必要があるかもしれません。
障害をオープンにしていれば、そういった際に職場の理解を得ることができ、結果として自分のためにもなります。
また、先ほども触れているように、ハローワークでは障害者であっても、仕事内容によっては一般の求人に応募できる場合もあります。
応募の際はハローワークの担当者が、障害があることをちゃんと伝えてくれるので、障害をオープンにしながらも健常者と同じ仕事ができる可能性も十分にあります。
もちろん障害をオープンにしなければいけないというわけではないので、最終的な判断は本人に委ねることになります。
しかし、どちらを選ぶにしても、オープンにした場合・しなかった場合でそれぞれどのようなことが起こるのかという点に関しては、しっかりと把握しておくようにしましょう。
各種支援を積極的に活用するのが有効
障害者の就労にあたっては、公的な機関や社会福祉法人、NPOなどでさまざまな支援を行なっています。
「障害者就業・生活支援センター」をはじめとし、『障害者就労支援センター(職業相談、就職準備支援、職場定着支援などの実施)』『就労移行支援事業所(障害者総合支援法に基づいた就労支援を行なう)』『地域障害者職業センター(職業リハビリテーションの実施)』、そして『ハローワーク』と多岐に渡るため、もし就職活動に悩んでいるのであれば、これらの機関を複数利用するのも1つの方法です。
まとめ
今回は障害者の就職について紹介してきました。
障害者の就職方法は健常者同様多岐に渡りますが、その中でもハローワークに関しては、各種支援をしっかりと行なってくれるので、利用しやすいのではないかと思います。
就職や転職に向けて何から始めればいいか分からないという人もいるかと思いますので、そういった場合はまずハローワークを訪れてみてはいかがでしょうか。
- 新着コラム
- 人気コラム
- おすすめコラム