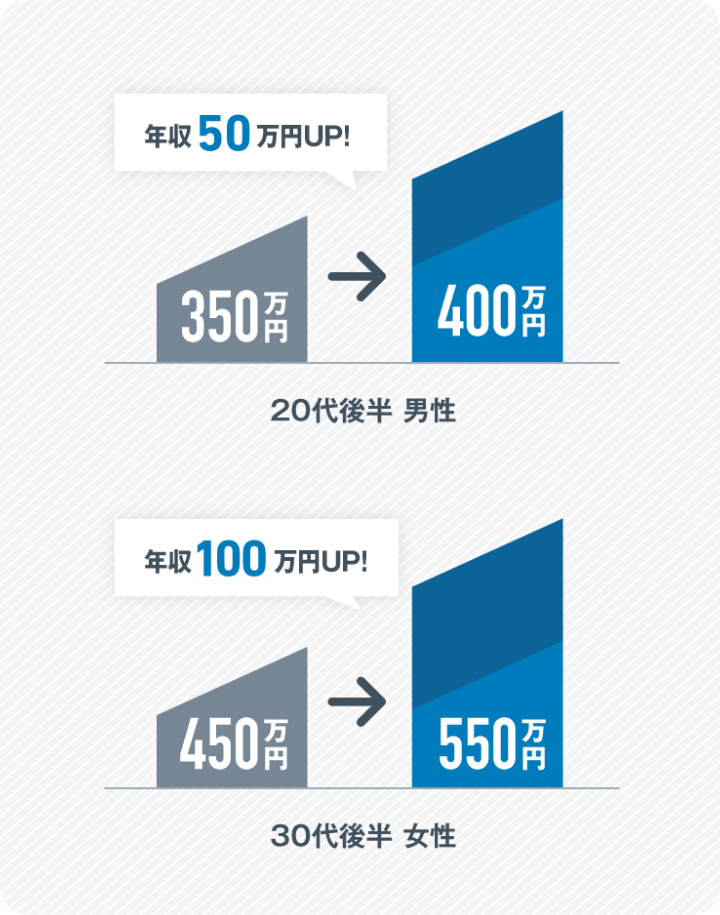本コンテンツには、紹介している商品(商材)の広告(リンク)を含みます。
ただし、当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。
退職したいのに強引に引き止められるトラブルが、日本では非常に多く発生しています。
実は法律上、労働者はいつでも自由に退職する権利を認められています。
しかし一部のブラック企業は、そうした労働者の権利を無視してでも自社の利益のために無理やり働かせようとするのです。
近年では労働者に代わって退職手続きを行う“退職代行サービス”の利用も増加していますが、未だに強引な引き止めは後を絶ちません。
退職トラブルがなくならない背景には、企業側の認識不足もあると考えられます。
辞めようとする労働者を説得するだけの“引き止め”であれば違法ではありませんが、脅迫・暴行などを伴う強引な引き止め行為は“在職強要”といって、違法な行為です。
今回は、適法な退職引き止めと違法な在職強要の違い、そして在職強要を受けた場合の対処法について解説します。
この記事に記載の情報は2021年04月14日時点のものです
退職代行を使ったからといって、退職の引き止め行為自体は違法ではない
正当な理由があれば直ちに違法となる訳ではない
冒頭でも述べましたが、退職を申し出た従業員に誠心誠意向き合って説得すること自体は違法ではありません。
たとえば、従業員が待遇への不満から退職を決意したと述べた場合に「待遇を改善するから思いとどまってほしい」などとお願いする行為です。
また「今は繫忙期なので、〇〇日まで待ってもらえないか」などと条件を交渉するのも違法ではないと考えられます。
あくまでも“譲歩をともなうお願い”であり、最終決定権は従業員に委ねられているからです。
在職を強要するような場合は違法性がある
一方、従業員の意思を無視して力づくで在職を強要する行為は違法です。
たとえば、
- 退職を伝えても無視され、大量の仕事を振られる
- 退職届を受理してもらえない、隠される
- 「辞めたら不利益を被ることになるぞ」などと脅迫される
- 「退職によって会社に損害が発生するので損害賠償請求をする」と脅迫される
- 「後任が見つかるまで待って欲しい」と期限が曖昧な条件で強引に引き止められる
などの行為です。
強引な在職強要をした場合の会社の罰則は?
在職強要は、従業員の意思を無視して力づくで働かせる悪質な行為。罰則はあるのでしょうか?
労働基準法第5条では「強制労働の禁止」を定めており、「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」としています。
もしご自分の置かれている状況が該当する場合は、企業側が「1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金」を科される可能性があります。
労働者の退職は原則自由
雇用期間の定めがある場合
契約社員、派遣社員、アルバイトなどの非正規労働者の場合は、3か月・半年・1年ごとに契約更新されるのでこちらに該当します。
原則として契約期間が終了するまで退職できませんが、やむを得ない事由(病気・ケガ・家族の介護など)があれば退職が認められる可能性があります。
さらに労働基準法第137条では、最初の契約から1年以上経過している場合は、いつでも退職することができると明記されています。
やむを得ない事由の判定も実際にはそこまで厳しくなく、全体的に“労働者の退職する権利”の方が重視される傾向にあります。
雇用期間の定めがない場合
一方、正社員の場合は、原則として「2週間前」に退職の意思を告げることによりいつでも退職できます(民法627条1項)。
この場合は「やむを得ない事由」のような制限がなく、理由は何でもOKです。様々な理由を一括して「一身上の都合」とすることも多いです。
年俸制・月給制など「期間によって報酬を定めた場合」には、「期間の前半までに」解約の申入れをすれば次期に切り替わるタイミングで退職できるとされています。
会社ごとに定められている就業規則と法律のルールが異なる場合には、原則として法律の方が優先されます。
もし会社にとって都合の良い就業規則のルールが法律よりも優先されると、法律によって労働者の権利を守ることができなくなるからです。
ただし就業規則で定められている退職の意思を伝えるタイミングが「1ヶ月前」ぐらいであれば、労働者を不当に拘束するとは言えず合理性が認められるケースが多いようです。
退職代行を使っても会社から引き止めが起こりえる3つの理由
後任が決まるまで退職できない
「後任が決まるまで待って欲しい」と引き止められることもあります。
会社側からの“お願い”という形で提案するだけなら違法ではありませんが、後任がいないことを理由に在職強要をするのは違法であると考えられます。
後任がいつ見つかるのかもわからないのに、それまで待つ必要はありません。適切な人材を確保しながら経営を回していくのは会社側の責任であって、あなたが不利益を被る必要はないのです。
社内規定を理由にする
就業規則で
- 「退職日の2か月前までに退職を申し出ること」
- 「上司の許可がなければ、退職することはできない」
などと独自のルールが定められていても、原則として法律が優先されます。
法律を無視した独自ルールが優先されるとなると、労働者の権利を守ることができなくなってしまいます。それでは、法律を作成した意味がありませんよね。
ただし「1か月前までに退職を申し出ること」ぐらいの範囲であれば、例外的に就業規則の方が優先されることがあります。
業界によっては「1か月」という期間に合理性があることもありますし、これぐらいの長さであれば労働者が大きな不利益を被るとは言えないからです。
損害賠償請求をされる
「退職によって会社に損害が発生するので、損害賠償を請求する」と脅されるケースもあります。
しかし労働者が正当な手続きで退職した場合、会社は損害賠償を請求できないとされています。
「労働者による悪質な犯罪行為によって会社の信用が傷ついた」などの特殊なケースを除いて、真面目に仕事をして退職しただけでは損害賠償を請求できません。
中には雇用契約や就業規則に罰金・違約金を定めているブラック企業もありますが、このような規定も違法となります。
在職強要への対処法3つ
労働基準監督署へ相談
在職強要を受けたら、まずは労働基準監督署に相談してみましょう。労働基準監督署のメリットは、無料であること。
平日訪問できない場合は、メール・電話などでも話を聞いてもらえます。
ただし労働基準監督署は必ず動いてくれるとは限りません。
動いてくれたとしても、企業への指導・命令が下されるだけで、あなたの直接の代理人として退職代行や損害賠償請求などをしてくれる訳ではありませんのでご注意ください。
退職代行の利用
民間企業による退職代行サービスは、顧客目線に立ったきめ細かな内容が特徴です。
費用の相場は25,000~55,000円ですが、LINE・電話・メールで24時間365日対応しているところがほとんどです。
会社に退職の意思を伝えるほかに、貸与品の返却、私物の回収など、面倒で憂うつ作業を代わりにやってくれます。
しかし弁護士と違って、慰謝料請求・未払い残業代請求などの法律事務ができない点には注意が必要です。
図:退職代行の基本的な流れ

弁護士に相談する
弁護士は、依頼人の個人の権利・利益のために戦ってくれる“法律の専門家”です。弁護士に依頼して、退職届の提出をしてもらうこともできます。
弁護士名義の退職届が内容証明郵便で届けば、企業側も姿勢を軟化させる可能性があります。
万が一労働審判・訴訟に発展した場合も弁護士がそのまま対応してくれるので、3つの手段の中ではもっとも“守られている感”が強いかもしれません。
【関連記事】退職代行を弁護士に依頼する7つのメリット|費用と非弁・失敗のリスクまで
まとめ
退職を思いとどまるよう説得するだけなら適法ですが、従業員の意思に反して力づくで引き止める“在職強要”は違法です。
労働者には、自由に退職する権利が法律で認められています。
万が一“在職強要”に遭ったら、労働基準監督署、退職代行サービス、弁護士のいずれかに相談しましょう。
それぞれにメリット・デメリットがありますから、
- 「緊急時の相談は24時間対応の退職代行サービス」
- 「慰謝料請求・未払い残業代請求は弁護士」など
臨機応変に使い分けることをお勧めします。