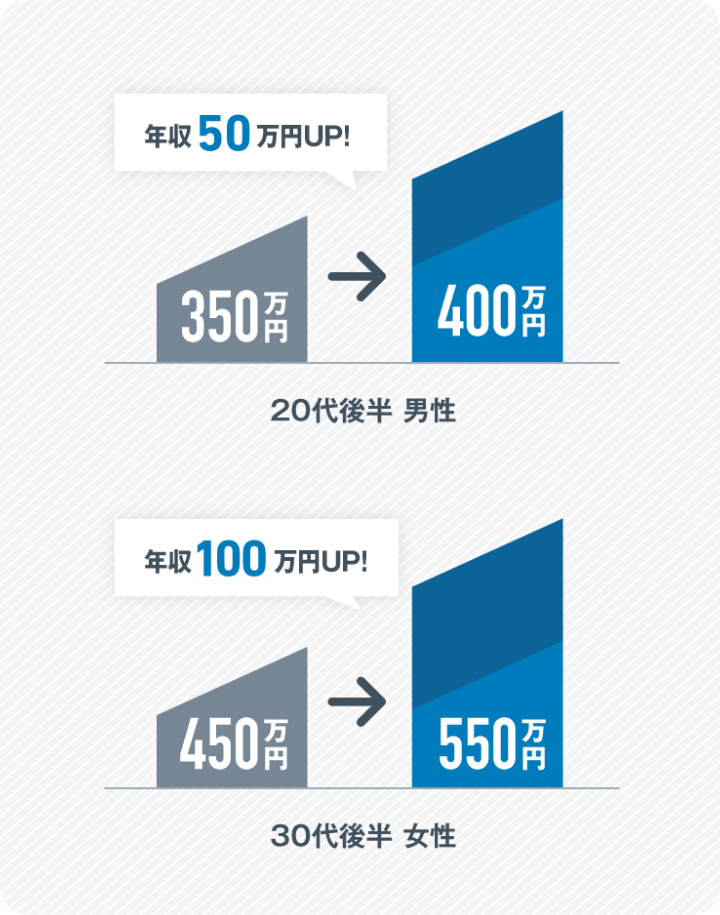本コンテンツには、紹介している商品(商材)の広告(リンク)を含みます。
ただし、当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。
退職代行を利用して会社を辞める場合、引き継ぎせずとも即日辞められるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
退職代行を使って会社に辞めたいと伝えたにもかかわらず、退職日まで出勤して引き継ぎ業務をしなきゃいけないなんて嫌ですよね。
結論から言うと、退職代行で引継ぎせずとも会社を辞めることは可能です。ですが、場合によってはトラブルを引き起こすリスクはあります。
そのため、引継ぎなしでの退職を希望する場合は、業者選びにも気を遣いたいところです。
この記事では、退職代行を利用した際に引継ぎなしで辞められる理由や、利用時によくある勘違いなどについて解説します。
退職代行を利用する場合に引継ぎなしで辞められる理由
退職代行を利用する以上、できれば面倒な引き継ぎ作業をしたくないというのが、本音ではないでしょうか。
実際、退職代行を利用して引継ぎなしで会社を辞められた方もいます。
なぜ、引継ぎなしで会社を辞められるのか、その理由を確認しておきましょう。
退職が有効になる2週間後まで有給を利用するから
退職代行利用時に、引き継ぎなしで辞められる理由の一つは、残った有給休暇を消化できるためです。
法律上は退職を申し出てから2週間が経過すると、雇用契約を解約できるとしています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法627条
また従業員が退職するにあたって、残っている分の有給休暇を利用することを会社は拒否できません。
そのため、退職日までの日数分の有給休暇が残っていれば、出勤せずとも会社を辞めることができます。
退職日を勝手に変更したり、有給休暇を買い取ったりすることはできないので安心してください。
合意があれば即日退職できる
会社が合意さえすれば、実は即日退職も可能です。当然、業務の引き継ぎ作業をする必要もありません。
気をつけてほしいのが、退職代行業者が行っている宣伝には「即日対応」と「即日退職」の2つがあります。
「即日対応」はお客様から相談があったら、連絡をすぐに返しますという意味で、「即日退職」とは無関係です。
また「即日退職可能」という記載があっても、100%できるわけではありません。前述したよう、あくまで会社が即日退職に合意した場合のみです。
退職代行業者に依頼した場合は交渉することができないため、会社が拒否してしまえば即日退職はできません。
長すぎる引継ぎ期間は無効だから
法律上は2週間で辞められるというものの、就業規則の「退職は〇か月前に申し出ること」という記載のどちらが優先されるのか、わからない方も多いかと思います。
基本的に優先されるのは民法の規定です。2週間より長い引継ぎ期間を設けていても、無効となる可能性が高いといえます。
就業規則によって引き延ばせるとしても、1ヶ月程度が限度。
仮に就業規則で「退職は3か月前に申し出ること」という記載があっても従う必要はなく、2週間前に退職を伝えておけば十分です。
ただし引継ぎしないことによるリスクもある
引継ぎなしで会社を辞めることに、リスクがないわけではありません。
例えば、引継ぎせずに会社を辞めたことで損害が発生したとして、損害賠償請求をされてしまう可能性はあります。
また、就業規則で引継ぎが不十分な場合には、懲戒処分にするとしている会社もあります。退職金の不支給や給料が減額されるかもしれません。
リスクを避けるのであれば、会社の備品を返却する、PC等のログインパスワードを伝えるなど、最低限の引き継ぎは行っておきましょう。
退職代行を利用する必要はない|出勤せずに辞めるための5つの手順
退職代行を利用したいという方の多くが、会社に出勤することなく辞めたいと考えているのではないでしょうか。
実は退職代行を利用せずとも、会社に出勤することなく辞めることは可能です。
会社を出勤しないで辞めるための5つの手順を紹介します。
STEP1|退職届を作成する
会社に出勤せずに辞めるためには、退職届を郵送する必要があります。
そのため、まずは退職届を作成しましょう。
退職届には、
- 会社名と最高責任者の名前
- 自身の署名と押印
- 退職予定日と退職届の提出日
- 「退職する」という旨
を記載してください。
また、退職予定日まで残った有給を利用するつもりであれば、「有給休暇申請書」も合わせて提出しましょう。
【退職届記載例】

STEP2|引き継ぎが必要な業務をまとめておく
前述したように、引き継ぎなしでの退職には、多少なりともリスクがあります。
そのため、事前に要点をまとめた引き継ぎ資料作成しておくとよいでしょう。
引き継ぎの資料には、以下のような内容を記載しておきます。
- 担当していた業務
- 業務フロー
- 業務で関わりのあった社内外の関係者
- 利用していたアプリやツールのID・パスワード
- 重要なデータの保存場所
- 業務に役立つノウハウ など
もっと簡易的な引き継ぎ資料でも問題ないですが、疑問点が残ってしまうと、退職後に連絡がくるかもしれないので注意が必要です。
STEP3|退職届を内容証明郵便で送る
退職届は配達証明付きの内容証明郵便で郵送しましょう。
退職届を普通の郵便で送ってしまうと、会社に届いていないと言い逃れされてしまう可能性があります。
配達証明付きの内容証明郵便を利用すれば、退職届が会社に届いたことを郵便局が証明してくれるため、後々揉める心配がなくなります。
参考:内容証明|郵便局
STEP4|退職日まで待つ
退職届を郵送したら、あとは退職日が来るまで待つだけです。とはいえ、会社から連絡が来ると思うので、一度は応じておいたほうがよいでしょう。
すんなりと退職を認めてくれる会社であれば、備品などの返却について説明があると思います。
仮に引き止めにあい、退職について同意が得られなくても、2週間を経過すれば辞められるので安心してください。
STEP5|万が一の場合は弁護士に退職代行を依頼する
会社によっては退職したいと伝えた際に、自宅に押し掛けてきたり、脅迫まがいの言動をとったりすることも考えられます。
自身で対応するのが困難な場合は、弁護士に退職代行を依頼しましょう。あなたに代わって会社と交渉をしてくれるため、自身で直接連絡を取らなくて済みます。
退職代行業者の場合は、弁護士とは違い、直接連絡をさせないということができません(会社に強制させることができない)。
そのため、ブラック企業と呼ばれる会社からの退職を考えているのなら、弁護士に依頼しましょう。
退職代行に関するよくある勘違い
最後に退職代行に関するよくある勘違いをまとめたので、確認しておきましょう。
退職代行業者が代わりに手続きをするわけではない
退職代行業者に依頼したからといって、退職に必要な手続きを代わりにしてくれるわけではありません。
退職届を作成したり、会社の備品を返却したりするのは自分自身です。
また会社が退職を認めてからは、連絡が滞る業者もいるため、かえって手続きに時間がかかってしまうかもしれません。
退職代行業者と弁護士のどちらに依頼しても費用は一緒
よく退職代行業者を利用するメリットに、弁護士より費用が安いことが挙げられますが、実は勘違いです。
退職代行に関しては、相場である3万~5万円で引き受けている弁護士は多いといえます。
最近では、相場以下の金額でサービスを提供している業者もありますが、その多くは流行りに便乗しているだけ。値段だけで選ぶのは危険といえます。
同じような値段を支払うのであれば、弁護士の依頼したほうがよいでしょう。
行政書士や司法書士による退職代行も非弁行為になる
最近では、退職代行に行政書士や司法書士も参入し始めています。
「専門資格を持っているから業者よりも安心」と思うかもしれないですが、行政書士や司法書士による退職代行も、非弁行為に該当する可能性が高いといえます。
弁護士とは違い、行政書士や司法書士に認められているのは一部の法律行為のみ。
現状、行政書士や司法書士に、退職代行が認められているとはいえないので、トラブルを避けたいのであれば、依頼しないほうがよいでしょう。
失敗することもある
退職代行成功率100%をうたっている業者も多いですが、必ずしも成功するとは限りません。
会社側も弁護士以外の退職代行に問題があることの理解が進んでおり、連絡が来た際の対策が取られ始めています。
依頼した業者が退職代行に失敗して、引き続き働くことになったケースもあるので注意しましょう。
まとめ
退職代行を利用した際に、引き継ぎなしで会社を辞められる理由は以下の通りです。
- 退職が有効になる2週間後まで有給を利用するから
- 合意があれば即日退職できる
- 長すぎる引継ぎ期間は無効だから
ただし、必ず引き継ぎなしで辞められる保証はないですし、少なからずリスクもあります。そのため、最低限の引き継ぎをしておいたほうが無難です。
また、退職代行を利用せずとも、会社に出勤せずに辞めることができます。
以下の手順に従って、退職手続きを進めてみて下さい。
- 退職届を作成する
- 引き継ぎが必要な業務をまとめておく
- 退職届を内容証明郵便で送る
- 退職日まで待つ
- 万が一の場合は弁護士に退職代行を依頼する
自分で会社に連絡を取らなくてはいけないですが、費用も郵便代くらいしか掛かりません。
ただ、会社によっては退職手続きを行わない、自宅に押し掛けてくる等の対応をとる可能性があります。
そうした場合には、弁護士に退職代行を依頼しましょう。費用も退職代行業者と同程度しか掛からないですし、失敗するリスクはほぼありません。
弁護士以外による退職代行は、非弁行為に該当する可能性があり、退職が認められない可能性があるので注意してください。