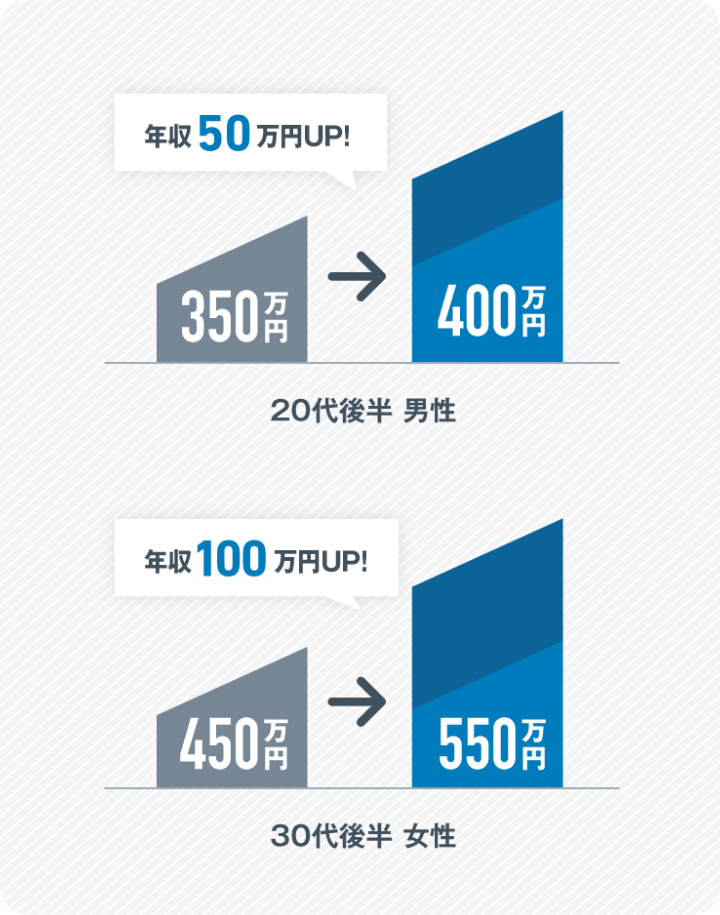難関資格で知られる中小企業診断士資格ですが、試験は1年に1度しかありません。
1年に1度のチャンスをものにするためにしっかり学習して試験に挑みたいものです。中小企業診断士の試験に合格するためには何時間程度の学習が必要なのでしょうか。
また、働きながらでも試験に合格することができるのでしょうか。中小企業診断士試験対策におすすめの勉強方法についても紹介します。
中小企業診断士試験の内容
中小企業診断士資格の試験は、1次試験と2次試験があります。1次試験は選択式の筆記で、2次試験は論述式の筆記試験と筆記試験に合格したら口述試験に進めます。
1次試験の科目は7科目、2次試験の事例は4問という構成です。
1次試験は科目合格制度があり、7科目のうち60%以上の点数を取得できたものがあれば翌年・翌々年その科目の受験が免除されます。
中小企業診断士試験の難易度は?
中小企業診断士の1次試験の合格率は、毎年20%~25%前後を推移しています。令和1年の1次試験は30.2%の合格率なので例年より高めでした。
2次試験の合格率は、20%前後です。令和元年の2次試験の合格率は18.3%です。1年で1次・2次試験ストレート合格を狙うとなると、非常に狭き門となることがわかります。


中小企業診断士試験合格に必要な勉強時間
中小企業診断士試験合格に必要な勉強時間について説明します。
一般的には1000時間必要と言われている
中小企業診断士の勉強は、まず基礎となる1次試験に800時間、2次試験対策に200時間で合計1000時間必要といわれています。
中小企業診断士の必要な勉強時間は1000時間以上と言われている。
— 鋼の天然水@独学 スタディング(studying)で中小企業診断士 (@shindan_hagane) December 10, 2020
でも勉強時間ベースで図るのは難しいよ。
だって銀行員やSEの人と知識のつかないブラック企業から一発逆転を狙っている人の前知識が同じわけないもん。
私はブラックから抜け出すために睡眠削りまくって診断士になったタイプ。
※もちろん、人によって変わるので一概にはいえませんが...
元の知識や実務経験で必要勉強時間は変わる
ただし、多くの人が苦手とする簿記や経済学の知識が実務ですでに身についている人は、財務・会計や経済学の科目でそこまでの勉強時間が必要ない場合もあります。勉強時間は元の知識や実務経験によるので、一概には言えません。
免除科目があるケースも
すでに保有している資格により、1次試験の科目が免除される場合もあります。このようなケースも、通常より勉強時間を抑えることができるでしょう。
- 公認会計士、公認会計士試験合格者、会計士補、会計士補となる有資格者、税理士、税理士試験合格者、税理士試験免除者、弁護士または弁護士となる資格を有する者
⇒財務・会計科目が免除 - 通算3年以上勤務する大学等の経済学の教授及び准教授・旧助教授、経済学博士、公認会計士試験または旧公認会計士試験第2次試験において経済学を受験して合格した者、不動産鑑定士、不動産鑑定士試験合格者、不動産鑑定士補、旧不動産鑑定士試験第2次試験合格者
⇒経済学・経済政策の科目が免除。 - 弁護士、司法試験合格者、旧司法試験第2次試験合格者
⇒経営法務科目が免除。 - 技術士(情報工学部門登録者に限る)、技術士となる資格を有する者、次の区分の情報処理技術者試験合格者(ITストラテジスト、システムアーキテクト、応用情報技術者、システムアナリスト、アプリケーションエンジニア、システム監査、プロジェクトマネージャ、ソフトウェア開発、第1種、情報処理システム監査、特種)
⇒経営情報システム科目が免除。
1次試験科目別勉強時間
1次試験では7科目の受験が必要で、約800時間~1000時間の勉強時間が必要といわれています。中小企業診断士を多く輩出している予備校のTACによると、合格者の勉強時間は1次試験・2次試験で1000時間が多かったとのことです。
1次試験の必要時間を800時間と仮定し科目数で按分すると、1科目あたり約115時間の勉強時間となりますが、実際には内容のボリュームや難易度で科目ごとの学習時間は異なります。令和2年試験の各科目別合格率もあわせて、各科目の内容や必要勉強時間の目安について説明します。
企業経営理論:150時間~200時間
企業経営理論は、「経営戦略論」「組織論」「マーケティング論」を勉強していきます。通信講座STUDYingの例でいうと、企業経営理論の講座は12のカテゴリーで分かれており最多です。そのため、按分の115時間では足りずに、勉強時間は150時間~200時間が必要といわれています。
この科目は単語の意味を問うような問題は少なく、問題文が独特の言い回しで複雑なのが特徴です。まずは単語の暗記を行い、その上で問題に慣れる必要があるので、過去問を何度も繰り返す必要がある点でも時間がかかります。
ただし、企業経営理論は中小企業診断士資格1次試験の主たる科目です。この科目が理解できていないと他の科目の理解も深まらないので、受講生が最も真剣に勉強する科目といえます。そのため、令和2年の科目合格率は19.4%と他教科に比べると高めです。
財務・会計:150時間~200時間
財務・会計は、簿記の資格を持っていたり、普段から財務・会計業務に慣れていたりする方にはそこまで難しくない内容です。
しかし、初学者の方は一から簿記や会計の基礎を覚える必要があります。STUDYingの講座では9のカテゴリーに分かれており、各カテゴリーで勉強する内容も多く、初学者が財務・会計を理解するには150時間~200時間は必要でしょう。
一次試験では電卓の持ち込みができませんので、普段から電卓に頼っている方は電卓なしで計算する練習が必要です。令和2年の科目合格率は10.8%と、難易度が高いのがわかります。
運営管理:100時間~150時間
運営管理は生産管理と店舗・販売管理の二分野に分けられます。製造や小売の現場をコンサルティングするために必要な知識を学ぶための科目です。
STUDYingの講座では9つのカテゴリーなので財務・会計と同じですが、各カテゴリーで学習するボリュームは少なく、財務・会計よりも少ない勉強時間でいいでしょう。
法則や原理・法律内容など、暗記で対応できる分野は約50%なので、暗記をすればするほど得点に繋がります。令和2年の科目合格率は9.4%と一番低いので、理解に自信がない場合には目安となる勉強時間は関係なく何回も繰り返して学習すると良いでしょう。
経営情報システム:100時間~120時間
情報技術に関する専門用語に慣れる必要がある科目です。IT分野で働いている人は得点しやすい科目ですが、ITの知識がない人は専門用語の理解・暗記に取り組む必要があります。
STUDYingの講座では7カテゴリーで他に比べるとボリュームが少なく、令和2年の科目合格率は28.7%と最も高い水準なので、按分の時間程度で問題ないでしょう。
経済学・経済政策:150時間~200時間
経済学・経済政策はマクロ経済とミクロ経済について出題されます。STUDYingの講座では7カテゴリーを学習しますが、グラフの読み取りなどの難易度が高いので、150時間~200時間は見込んでおいたほうが良いでしょう。
経済のトレンドを問う問題もあるので日経新聞の購読もおすすめです。令和2年の科目合格率は23.5%でしたが、過去5年間合格率は20%を超えています。難しいテーマですが、テーマがはっきりしているため勉強すれば得点できます。
経営法務:70時間~100時間
経営法務は、毎年合格率が5%から10%と難関科目です。令和2年は12.0%と例年に比べると高めですが、他教科に比べると毎年低水準で推移しています。
法律問題独特の言い回しが難しく感じる原因です。会社法・知的財産権・民法・資本市場における法律知識から出題されますが、深堀して勉強しだすと勉強を終えられなくなってしまいます。すべてを深く学ぼうとせず、頻出の民法と知的財産を中心に勉強するといいでしょう。
STUDYingの講座では7カテゴリーと少なく、前述の通り深堀しすぎないほうがいいので70時間~100時間ほどの勉強時間を目安にしてください。
中小企業経営・政策:50時間~70時間
中小企業経営・政策は毎年4月に発行される中小企業白書を元に出題されます。
政府等が行っている中小企業向けの各種政策の問題が出題されますので、金融サポート、財務サポート、経営サポートでどんな政策が行われたかなどを確認します。STUDYingの講座では7カテゴリーで、2次試験との関連性も低いのでそこまで重点的に学習する必要はないといわれています。
そのため、学習時間は50時間~70時間程度にしておきましょう。令和2年の科目合格率は16.4%でしたが、令和1年は5.6%と変動が大きい科目です。完全に暗記問題なので、しっかり中小企業白書を読み込んで暗記するほど得点は伸びるでしょう。
2次試験の勉強時間
次に2次試験の勉強時間について紹介します。
2次試験は筆記試験+口述試験
2次試験の論述式の筆記試験にかける勉強時間は200時間程度必要といわれています。1次試験から2次試験のまでは例年3カ月ほどしか時間がないので、ストレート合格を目指すのであれば、1次試験の合格がわかる前から2次試験の対策をする必要があります。
また、論述式の筆記試験は独学だと「方向性が合っているか間違っているかわからない」という状態になる可能性が高いです。1次試験を独学で合格できた場合も、2次試験の対策は予備校などで回答を添削してもらったほうが効率の良い学習に繋がるかもしれません。
口述試験については、ほぼ100%が合格します。形式的な試験なので特段勉強をする必要はありません。遅刻をせず、清潔感のある身なりで臨み、試験官の質問に落ち着いて回答できれば特段問題ないでしょう。
2次試験は中小企業診断士の養成課程を受講すれば免除
中小企業大学校や大学が開校する養成課程を受講すれば、2次試験の受験は免除になります。
この養成課程は全日制の場合は半年、土日に開校されるものの場合は2年ほどかかります。また、費用も200万円ほどかかるので負担もありますが、より実践的な知識を得たい場合には養成課程を受けたほうが良いといえるでしょう。
働きながら中小企業診断士試験の合格は可能?
中小企業診断士資格は30代~40代に人気の資格で、ほとんどの人が働きながら資格取得を目指します。働きながら資格試験で合格するためには以下のスケジュールがおすすめです。
- 平日2時間×5日
- 休日5時間×10日
- 25時間×4週間=100時間(1カ月)
約1年勉強し続ける必要がありますが、決して無理ではないといえるでしょう。受験に際しては、本人の努力はもちろんですが職場や家族の理解も必要といえそうです。
中小企業診断士試験に効率的に合格するには予備校がおすすめ
中小企業診断士試験は独学で勉強することも可能ですが、特に働きながら受験を目指す場合には出題範囲が広く独学には向いていないといわれています。1年に1回のチャンスをものにするためには、予備校に通うか通信講座を利用して効率的に学習するべきといえるでしょう。
予備校に通うと「絶対に勉強しなければいけない」という環境に身を置くことができます。また、他の受験生の顔を見ることで、「自分も負けずに勉強しよう」というやる気も生まれるでしょう。ここでは、中小企業診断士資格取得におすすめの予備校を紹介します。
アガルート
アガルートの中小企業診断士講義は、オンラインで視聴できます。講師が作成したフルカラーのテキスト(冊子)が視覚的に見やすいと評判です。
各科目の講座を網羅した総合講義は88,000円、総合講義に過去問がついた総合カリキュラムは98,000円です。科目ごとの受講も可能なので、集中的に学習したい科目だけ講座を購入ということもできます。
参照:中小企業診断士試験|総合カリキュラム | アガルートアカデミー (agaroot.jp)
STUDYing
STUDYingは、講座視聴から問題集まですべてスマホで学習が完結する作りになっているのが大きな特徴です。講師は中小企業診断士資格を保有する、企業の代表でもある綾部講師です。
綾部講師が自らの中小企業診断士試験受験にてこずった経験をもとに、通勤時間に学習できるようにカリキュラムが設計されているのがポイントです。
STUDYing受講のメリットは、他社と比べて価格が抑えられていることです。1年で1次・2次試験合格を目指すコースは、53,790円で、通学式の講座に比べると約4分の1となっています。ただし、紙ベースのテキスト・学習マップは別売りなので、紙に書き込んで勉強をしたい場合には別途15,180円の支払いが必要です。
参照:中小企業診断士講座 - スマホで学べる通信講座で資格を取得 【スタディング】 (studying.jp)
TAC
TACでは、受講生のスケジュールや勉強状況に合わせて様々なコースが用意されています。初学者が1年で1次・2次試験の合格を目指すコースは通学とWeb受講を合わせたカリキュラムが264,000円と入学金10,000円で受講できます。疑問点は直接講師へ即質問できること、勉強仲間が作れることがメリットです。通学は平日夜や土日なので、仕事をしながらでも勉強できます。
参照:中小企業診断士|資格の学校TAC[タック] (tac-school.co.jp)
資格の大原
大原の提供する中小企業診断士試験1次2次試験合格を初学者が1年で目指すコースは、教室通学が298,000円、Web講座が268,000円です。通学は週2回の通学ペースなので、働きながらでも無理なく知識を身に着けることができます。
2次試験の論述式は、通信講座だと値段は安くても添削サービスがないものがほとんどですが、大原の場合は経験豊富な講師に添削してもらえるのがメリットです。
参照:中小企業診断士 | 資格の大原 社会人講座 (o-hara.jp)
LEC 東京リーガルマインド
LEC東京リーガルマインドの中小企業診断士資格取得コースは、1年で1次試験合格を目指すコース、初学者向けに1.5年で資格取得を目指すコース、2次試験合格を目指すコースなどを提供しています。
初学者が1.5年で1次・2次試験の合格を目指すコースは、通学/通信を組み合わせたWeb受講が286,000円、DVD受講が330,000円です。科目合格制度を利用して、1年目で4科目を確実に合格し、2年目で残り3科目と2次試験合格を目指す設計になっています。
参照:中小企業診断士|LEC東京リーガルマインド (lec-jp.com)
診断士ゼミナール
診断士ゼミナールの中小企業診断士コースは、スマホやタブレットで講座の視聴が可能です。1次・2次試験対策ができるプレミアムコースは54,780円と他社に比べても費用が抑えられており、過去問が5年分もついているのも嬉しいポイントです。テキストは別途購入が必要ですが、フルカラーで視覚的に覚えやすい配慮がされています。
また、診断士ゼミナールの講座はゼネラルリーサーチの調査で、「講座のわかりやすさ」「顧客満足度」「継続しやすさ」4年連続1位を獲得しています。(中小企業診断士講座10社の比較)
参照:診断士ゼミナール (rebo-success.co.jp)
まとめ
中小企業診断士合格のためには、1次試験・2次試験合わせて約1000時間の勉強時間が必要といわれています。働きながらでも合格を目指すこともできますが、約1年間の勉強時間が必要だと思っておいたほうが良いでしょう。
中小企業診断士の試験範囲は7科目あり、出題範囲が広いのが特徴です。独学で学習することも可能ですが、効率的に学習したいのであれば予備校や通信講座を利用すべきといえます。
予備校は、必ず勉強しなければいけない環境に身を置ける、勉強仲間ができる、講師に質問ができるといったメリットがあります。通信講座は、自分のペースで学習できる、費用が安いといった点がメリットです。
それぞれにメリットがありますので、ご自身に合った勉強法を選択し、効率的に試験合格を目指しましょう。
転職・人材業界に深く関わるディレクターが『今の職場に不満があり、転職を考え始めた方』や『転職活動の進め方がわからない方』へ、最高の転職を実現できる情報提供を目指している。
本記事はキャリズムを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※キャリズムに掲載される記事は転職エージェントが執筆したものではありません。
- 新着コラム
- 人気コラム
- おすすめコラム