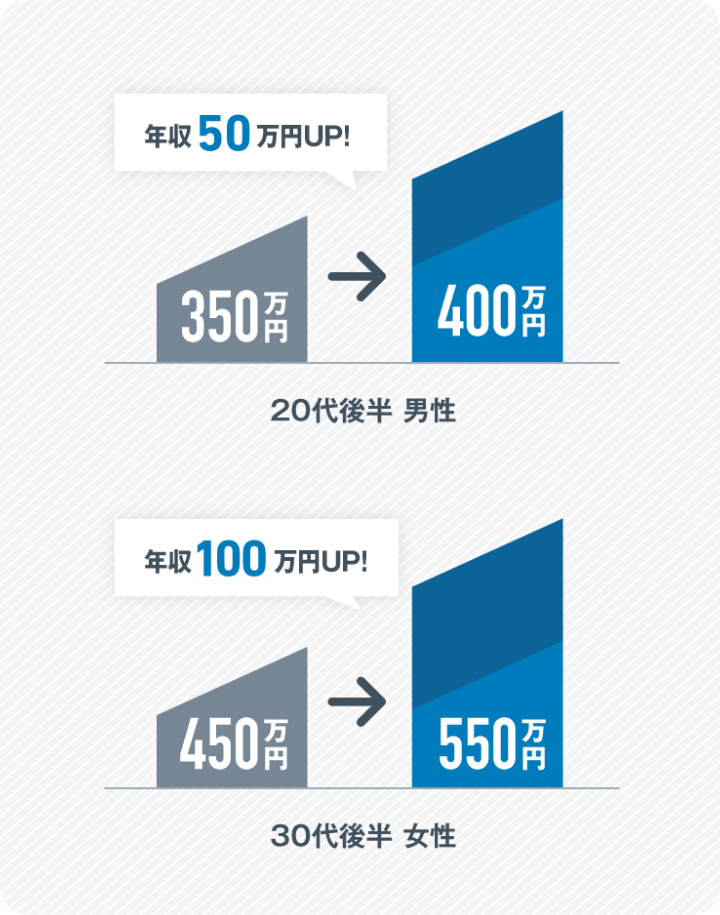「公認会計士試験の難易度は高い」と思ってこちらのページにたどり着いた方も多いことでしょう。先にお伝えすると、公認会計士試験の合格率は毎年10%程度で、これだけをみれば、決して難易度が高すぎるものだとは言えません。
しかし、他にも覚える量や科目の多さ、必要勉強時間数の多さなどから、難易度が高い資格と結論付けることが言えます。
もし、収入の良さや受験資格がない国家資格という理由だけで公認会計士試験を目指している方がいるのであれば、「ちょっと待って考え直して!」と、言えるくらい簡単に目指せる資格・職業ではありません。
こちらの記事では、公認会計士試験の難易度を様々な観点からご説明します。
公認会計士試験の難易度は非常に高いのは事実|合格率は約10%
冒頭でお伝えした内容をまとめると、公認会計士試験の難易度は高いと結論付けることができます。実際にどれくらいの難易度かイメージしにくいでしょうから、例や数字を用いりながらご説明します。
公認会計士は三大資格の1つ
公認会計士の資格は三大資格の1つと言われており、資格取得の難易度も非常に高いと言えます。
- ≪三大国家資格≫
- 公認会計士
- 医師
- 弁護士
三大資格については、人によっては『医師』の部分が『不動産鑑定士』に変わっていることもありますが、公認会計士についてはいずれも入っていますので、とにかく難易度もレベルも高い資格と言えるでしょう。
医師や弁護士であれば、医学部や法学部などを卒業し、限られた人のみが取得する資格との認識もありますね。そのため、すでに大学を出て働いている方などが、改めて医師や弁護士を目指そうと志すことも珍しいことだと思います。
一方で、公認会計士には受験資格がありません。学歴や経験問わずに誰でも挑戦できる資格なのですが、いざ資格取得のために色々調べてみると、とんでもない難易度の高さで驚いている方も多かったのではないでしょうか。
公認会計士試験の合格率は約10%

公認会計士試験の合格者率は毎年10%程度を推移しており、1,000人強の人が毎年合格していることになります。この合格率10%という数字だけを見ると、決して難易度が高すぎるものとも言えなさそうです。
|
順位 |
資格 |
合格率 |
|
1位 |
司法書士 |
4.4% |
|
2位 |
社会保険労務士 |
6.2% |
|
3位 |
弁理士 |
8.1% |
|
4位 |
公認会計士 |
10.1% |
|
5位 |
行政書士 |
10.7% |
他の資格と比較してみても、合格率1ケタ台の資格はありますが、この中では公認会計士が圧倒的に難易度が高い資格です。合格率が低い資格は、受験のしやすさなども影響しているからでしょう。
例えば、社会保険労務士は日々の労務の仕事と直結した科目も多いため、働きながらの資格取得を目指している人も多いです。
しかし、公認会計士は資格取得者でないとできない業務も多く、勉強時間も膨大になるため、働きながらの資格取得は非常に困難となります。これらの理由も公認会計士は難易度が高いと言われる所以でしょう。
公認会計士の難易度が高いと言われる5つの理由
公認会計士の難易度が高いと言われる理由について、勉強時間や勉強範囲などの観点を主にもう少し詳しくご説明していきます。
3,000~5,000時間程度の学習が必要
試験合格のためには、どの資格でも勉強が必要ですね。公認会計士の場合、3,000~5,000時間程度の勉強時間が必要だと言われています。数字だけだとピンと来ないでしょうから、例を挙げます。
まず、3,000時間以上の勉強時間は、東大合格を目指す人の勉強時間と同等と言えます。
また、3,000時間以上の勉強をしようとすれば、1日6時間学習を毎日2年間休まず行う必要があります。
現在働いていなくて、資格取得に専念できる立場の方であれば、十分確保できる時間ですが、働きながらとなると、仕事と睡眠以外はすべて勉強に費やすくらいの覚悟が必要です…(しかも2年間)。
【関連記事】公認会計士試験に合格するまでに必要な勉強時間の目安は?
学習・出題範囲が広い
公認会計士試験では、必須科目も多く学習範囲が広くなることも、難易度が高いと言われる理由でしょう。公認会計士試験のために勉強する科目をまとめると以下の通りです。
|
必須科目 |
選択科目(論文式試験で1科目選択) |
|
|
必須5科目はまんべんなく勉強する必要があり、残りの選択科目も早い段階から決めておき、合計6科目分の勉強はしなくてはなりません。
それぞれの科目をマスターするためにも300~1,000時間の勉強が必要になるため、結果的に合計3,000時間以上の勉強が必要になってくるのです。
試験内容が複雑
科目が多く覚える範囲が広いとお伝えしましたが、そもそも公認会計士で取り扱う内容が複雑で難しいです…。財務会計論・管理会計論では、計算方法を覚えるだけでははく、仕組みやそうなる意味までしっかり理解しておく必要があります。
企業法では、法律が大きく関わりますので特有の言い回しを理解し、条文・立法趣旨・要件・効果などの全体を理解していかなくてはなりません。
監査論は専門用語も多く、普段の生活では関わることがほぼ無い内容ですので、噛み砕いて理解することから始めます。とにかく、どの科目も非常に複雑で、それでいて量も多いため難易度が高いと言われているのです。
一発合格が必要
公認会計士試験は『短答式試験』と『論文式試験』の2段階になっており、短答式試験に合格した人が次の論文式試験に挑戦する流れとなります。
言い換えると、短答式試験に合格しないと論文式試験を受けることもできなくなるため、基本的に一発合格を目指します。
短答式試験に合格した人はその後2年間論文式試験を受ける資格があるため、翌年以降に再挑戦することも可能ですが、もし2年以内に論文式試験で合格できなければ、短答式試験からやり直すこととなります。これが公認会計士試験の難易度の高さの1つです。
例えば、税理士試験であれば、1科目ずつ合格していってもよく、最終的に5科目を合格できれば税理士資格を取得できます。公認会計士試験では、悠長に何年もかけて受験することができないため、一度にまとめて勉強時間を確保する必要が出てきてしまうのです。
働きながらだとさらに難易度が上がる
働きながら公認会計士試験を目指している方がこちらをご覧になっているかもしれません。その方には少し厳しい内容にはなりますが、働きながら公認会計士試験を目指そうとすれば、さらに難易度は上がります…。
やはり勉強時間の確保が難しくなることが一番の理由でしょう。

参考:令和2年公認会計士試験合格者調|公認会計士・監査審査会
公認会計士試験に合格した人のうち、会社員は7.1%しかいませんでした(ちなみに社会人のみの合格率は3.8%です)。ほとんどが学生や無職などの試験勉強に専念できる状況の人で、全体の8割以上を占めます。
働きながらの公認会計士資格取得は絶対に無理というわけではありませんが、かなり難易度が上がることは認識しておきましょう。
公認会計士の難易度を下げるにはとにかく効率的に勉強すること
ここまでご説明した通り、非常に難易度が高い公認会計士試験ですが、少しでも難易度を下げるためには、効率的に学習することを目指してください。
本質を理解している受験生が受かる…
— 資格の大原 会計士 (@o_hara_kaikei) January 12, 2020
と思ったことは一度もありません。
むしろ,「とにかく覚えればいいっすよね?」みたいな受験生が早く受かります。
最近,受験生の間に「深く理解せねば」という雰囲気を感じますが,
そういう高尚な試験ではないので,
やめて欲しいです。。
(統計学:井口)
言葉足らずで少し炎上しかけたツイートではありますが、講師の先生もとにかくは覚えることを優先した人が受かりやすいともおっしゃっています。
真面目な人ほどつい本質まで理解しようと深みにはまっていきますが、まず合格を目指すのであれば、限られた時間でどう効率的に必要な分だけを勉強していくかを模索していきましょう。
1科目ずつ集中して覚える
公認会計士試験は、必須科目5+選択科目1で挑みますが、まずは1科目ずつ集中して覚えていきましょう。人にもよるでしょうが、いくつもの科目を同時期に勉強するやり方は非効率です。
まずは1科目ずつテキスト等で知識を得ていき、過去問まで解けるようにします。それを次の科目でも繰り返し、最終的に模試等で全部の科目の問題を解く練習をしていきます。
|
科目 |
勉強時間 |
|
財務会計論 |
約1,000時間 |
|
管理会計論 |
約300時間 |
|
監査論 |
約300時間 |
|
企業法 |
約300時間 |
|
租税法 |
約300時間 |
|
選択科目 |
勉強時間 |
|
経営学 |
約200時間 |
|
経済学 |
約500時間 |
|
民法 |
約400時間 |
|
統計学 |
約200時間 |
それぞれの科目の勉強時間の比率・目安については上記の通りです。この内容を元に、試験までの残り期間を考えながらスケジュールを立てていき、1つ1つ学んでいく方法が効率的だと言えるでしょう。
教材・予備校・通信講座を有効活用する
合計3,000時間以上が必要になってくる公認会計士試験の勉強では、独学だけでは非常に困難だと言えます。勉強に付いていけなかったり、途中でモチベーションが維持できなくなって挫折してしまう可能性を高めてしまいます。
公認会計士試験のための予備校や通信講座を利用しようとすれば70万円~100万円程度の費用はかかってきてしまいますが、今後公認会計士として活用できれば余裕で返せてしまう程度の金額です。
本気で合格を目指すのであれば、何かしらの学習教材を使うことを検討しましょう。時間・場所で融通が利きやすい、通信講座も利用できる資格講座を3つご紹介します。
公認会計士試験の試験合格におすすめの資格講座3つ
TAC

TACは、いま最も公認会計士の合格者を輩出している予備校です。新試験制度制定後 2006年~2019年公認会計士論文式試験におけるTAC本科生合格者累計実績は、8,617名にも達しています。
- ≪TACの特徴≫
- 公認会計士試験に合格した優秀な講師がいる
- 講師全員が元受験者
- 予想問題の精度が高い
▶「TACの公認会計士サイト」はこちらから。
LEC東京リーガルマインド
LECは、「リーガルマインド」という名前の通り、法律に強い予備校で、公認会計士試験にも力を入れています。特に、短答式に特化していて、1年で合格を目指すためのカリキュラムも組まれています。
- ≪LECの特徴≫
- 通信講座が好評
- 板書やレジュメをPDFでダウンロードできる
- 短答式と論文式のカリキュラムが分かれている
▶「LECの公認会計士サイト」はこちらから。
CPA会計学院

CPAは、働きながら合格することも目指しており、時間や場所に制限を受けない通信講座が魅力的です。公認会計士の初学者にも経験者にも合ったカリキュラムが整っています。
≪CPAの特徴≫
- 考え方に重きを置いたテキスト
- 手厚い個別フォロー
- 通信講座であっても一部なら教室で受講可能
▶「CPAの公認会計士サイト」はこちらから。
公認会計士試験よりも難易度を下げた資格は?
ここまでの内容をまとめると、公認会計士試験の難易度は非常に高いという結論にまとめることができます。特にすでに社会人として働かれている方は、勉強時間の確保が難しくなってきますので、さらに難易度は上がります。
とは言っても、新たに資格取得に挑戦する姿勢は素晴らしいものですし、もちろん少しでも可能性があるのであれば、公認会計士試験も諦めてはいけません。ただ、どうしても勉強時間が確保できない方や1~2年ちゅうに資格を取りたいと考えている方は、公認会計士試験よりも少し難易度を下げた資格も検討してみてください。
公認会計士でも関係する分野の資格もありますので、将来的に公認会計士に再挑戦することも可能ではあるでしょう。
簿記検定|2級以上
ご存知、簿記検定では財務会計についての知識を得られて証明することができる資格です。3級だと個人・商店規模の会計になるため、あまり企業からは求められない資格ですが、2級以上の資格を持っていれば、転職などでも有効に働きます。
特に1級まで取得できれば、経営分析やコンサルティングにも活かせる資格となるため、それらの仕事にも就きやすくなります。
簿記検定1級の試験科目『会計学』は、公認会計士の試験科目にもあるため、簿記検定1級に合格すれば、公認会計士で求められる簿記レベルに達することもできるでしょう。
税理士
税理士試験では、『科目合格制』を採用しており、科目単位での合格が認定され、5つの科目を数年かけて合格することで税理士資格が取得できる仕組みとなっています。
この科目合格制により、働きながらの資格取得もしやすくなっており、結果、税理士試験では40代の合格者が一番多い割合となっています。
税務は、公認会計士でも関係する業務であるため、税理士資格を取得した後に公認会計士試験に挑戦される方もいます。
まとめ
公認会計士の難易度は高いです。まず、三大国家資格の1つと言われており、弁護士・医師(もしくは不動産鑑定士)に並ぶほどの強い影響力と難易度の高さを持つ資格です。
公認会計士試験の合格率は近年10%程度を推移しており、これは他の国家資格の中でも合格率が低い資格の5番目以内に入ります。
合格するためには最低でも3,000時間の勉強が必要で、なおかつ内容は複雑です。
受験資格はなく、誰でも受けることができる公認会計士試験ですが、やはり難易度は非常に高いです。ここまでお読みいただいた方にはいないでしょうが、もし安易な気持ちで公認会計士試験を受けてみようと考えていた方は、慎重に考え直してみてください。
難易度が高くても挑戦するという方は、効率的な勉強方法の確立とスケジュールの組み立てを行い、コツコツと日々の勉強に専念していってください。
転職・人材業界に深く関わるディレクターが『今の職場に不満があり、転職を考え始めた方』や『転職活動の進め方がわからない方』へ、最高の転職を実現できる情報提供を目指している。
本記事はキャリズムを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※キャリズムに掲載される記事は転職エージェントが執筆したものではありません。
- 新着コラム
- 人気コラム
- おすすめコラム