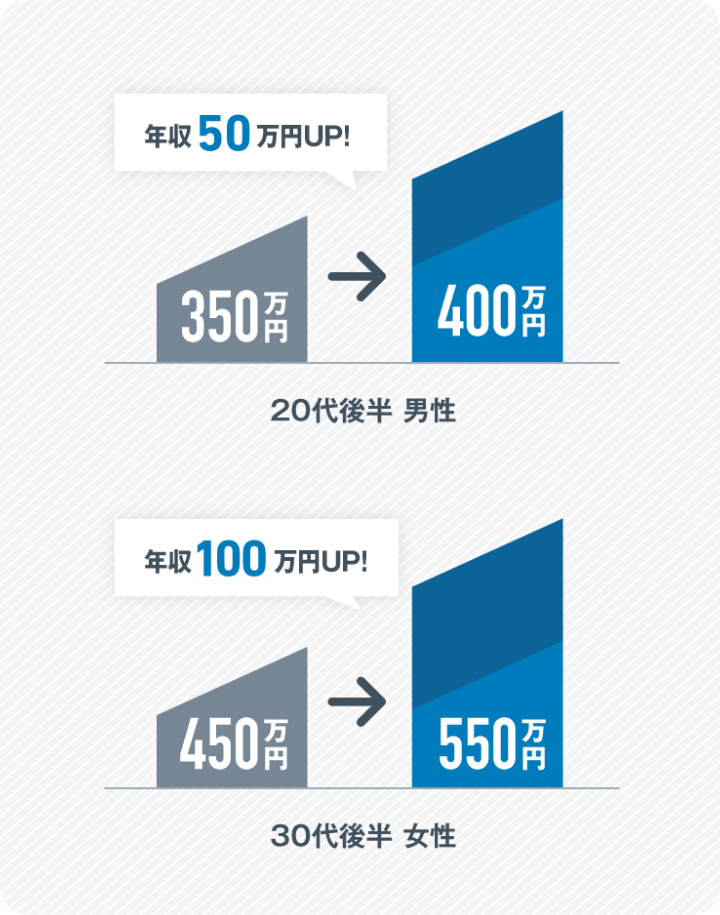本コンテンツには、紹介している商品(商材)の広告(リンク)を含みます。
ただし、当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。
「税理士資格を独学で取得することなんてできるの?」
「税理士資格の難易度を知って独学で取得できるか判断したい!」
「独学で税理士資格を取得するためにはどうしたらいいの?」
このような疑問や考えをお持ちの人もいるでしょう。税理士資格は難関ですので、そう簡単に合格することはできません。
そのため、税理士の資格スクールに通う人は多くいます。しかし、経済的な理由や時間的制約によって、独学で税理士資格を取得しようとする人もいるのです。
本当に税理士資格を独学で取得することは可能なのでしょうか。この記事では、合格難易度や独学のメリット・デメリットなどを整理しましょう。
独学での税理士資格の取得を考えている人はぜひ読んでみてください。
税理士資格試験は独学でも突破可能?
まず、結論から言うと、独学での合格は難しいのが現実だとお伝えしたいです。ほとんどの受験生がTACやLEC、大原といった資格スクールに通っています。それは、税理士資格の取得難易度が高いためです。
単純に試験問題が難しいだけでなく、満点を狙うのではなくいかに合格ラインに乗せるかと言った、いわゆる受験テクニックが求められます。
その合格テクニックを自らの力で打破できるのでしたら問題ありませんが、そう容易いことではなく、資格スクールで学んだ方が効率化できることもしばしばです。
【2020年最新版】税理士資格試験の難易度とは|合格率は15.3%
「税理士資格は難しい」と言っても、どれほどの難易度なのか分からない限り、自分にとってどれほど難しいのか判断ができないでしょう。
そこで、国税庁が発表している令和元年度(第69回)税理士試験結果表(科目別)を見てみましょう。

引用元:国税庁│令和元年度(第69回)税理士試験結果
元年度合格率は、11.7%~19.0%の間です。前年度もそう大差ありません。科目によって合格率に差があるので、「どの科目を選ぶか?」というのも重要な戦略だと言えます。
例えば、会計事務所での勤務経験がある人にとって所得税や法人税、消費税といった科目は実務と重なるところがあるので頭に入ってきやすいようです。
学習のしやすさは個人差があるはずですので、科目選びにもこだわってみてください。
税理士試験の受験資格は?
税理士試験の主な受験資格はこちら。
学識による受験資格
- 大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で、法律学又は経済学を1科目以上履修した者
- 大学3年次以上で、法律学又は経済学を1科目以上含む62単位以上を取得した者
- 一定の専修学校の専門課程を修了した者で、法律学又は経済学を1科目以上履修した者
- 司法試験合格者
- 公認会計士試験の短答式試験に合格した者
資格による受験資格
- 日商簿記検定1級合格者
- 全経簿記検定上級合格者
- 職歴による受験資格
- 法人又は事業行う個人の会計に関する事務に2年以上従事した者
- 銀行、信託会社、保険会社等において、資金の貸付け・運用に関する事務に2年以上従事した者
- 税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助事務に2年以上従事した者
参考:国税庁│税理士試験受験資格の概要
上記は受験資格のうち、主なものです。国税庁サイトの「受験資格について」にて、詳しく説明されています。
意外と多くの受験資格条件が認められていることに驚かれるのではないでしょうか。税理士試験を受ける資格は多くの人に与えられています。
資格勉強時間に約2000時間は本当か!?
税理士資格の勉強にどれほどの時間を費やすことになるのか、不安な気持ちを抱きながら気になるかもしれません。よく専門学校で言われるのは以下のような勉強時間です。
|
簿記論
|
450時間
|
|
財務諸表論
|
450時間
|
|
所得税法
|
600時間
|
|
法人税法
|
600時間
|
|
相続税法
|
400時間
|
|
消費税法
|
250時間
|
|
酒税法
|
150時間
|
|
国税徴収法
|
150時間
|
|
住民税法
|
200時間
|
|
事業税
|
200時間
|
|
固定資産税
|
250時間
|
しかし、もちろん個人差があることですので、あくまでも目安と考えてください。
とはいえ、独学で税理士資格を取得するなら、これだけ多くの時間を一人で集中して取り組まないといけません。それ相当の覚悟が必要ですね。
働きながら試験合格は目指せる?
働きながら、税理士資格の合格を目指す人も多いです。税理士試験は1回の試験で5科目全てに合格しなければいけないわけではありません。毎年コツコツ1~2科目を取り組んでいる人もいます。
ただし、働きながら「短期間で」税理士試験に合格するのはなかなか大変なことですので、長期的な視野で考える方がよいでしょう。
5~10年くらいなら、働き続けながら勉強するのも苦ではないというスタンスくらいが必要です。
【比較】税理士を独学で目指すのと資格スクールに通う場合のメリット・デメリット
ここで一度、独学と資格スクールのメリット・デメリットを比較してみましょう。自分の性格や生活、状況などと照らし合わせて考えてみてください。
独学のメリット
- 自分のペースで学習を進められる
- 費用が安く済む
- いつでもどこでも学習できる
独学の最大のメリットは、自分の理解度に合わせて勉強する範囲や量、スピードを自分でコントロールできるところです。たしかに我流にはなると思いますが、勉強スタイルを確立できたら、独学のメリットを大きく感じるでしょう。
また、資格スクールにかかる費用を節約できるのも大きな利点です。資格スクールや学習期間、コースによってさまざまですが、必要な学費の目安が100万円とも言われています。
決して安くないので基礎的な勉強は独学で行おうという考えも出てくるでしょう。
そして、独学ですと資格スクールに通う必要がないので、自宅でも通勤のあいだでも好きな時間に勉強できます。
働きながらの勉強ですと、日によって残業が発生するので、資格スクールに通いにくいこともあるでしょう。独学ですと、働きながらでも調整できます。
独学のデメリット
- モチベーションを維持しにくい
- 税法科目のテキストが充実していない
独学の最大のデメリットは、数年をかけて税理士試験の5科目に合格することになる人がほとんどですので、モチベーションを保つのが大変なことです。
とりわけ独学は自分で模索しながら学習することもあるので、余計に時間がかかるかもしれません。明確な意志がないと、続けにくいでしょう。
また、税法分野についての市販テキストがあまり充実していないこともデメリットとして挙げられます。書店で販売されるテキストでは最新の税制改正に追いつかず、資格スクールで使用しているテキストでないと学びにくいという特徴があるのです。
資格スクールに通うメリット
資格スクールに通うメリットはこちら。
- 【通信講座の場合】受講する時間・場所を選ばない
- 【通信講座の場合】2倍速の早送りもできる
- 【通信講座の場合】資格スクールに通う交通費がかからない
- 【通学講座の場合】勉強の強制力が働く
- 【通学講座の場合】ほかの受講生から刺激を受けられる
通信講座と通学講座とではメリットが異なります。
通信講座の場合、受講する時間や場所を選ばないので出勤前のカフェや通勤時間を活用している人も多くいます。通学講座よりも比較的に費用が安いのもよい点ですね。
また、2倍速で講座を聞いている受講生も多いようです。効率よく勉強をするために習得した学習方法ですね。
通信講座ですと、資格スクールに通う交通費がかからないので、コストを抑えられます。とりわけ地方だと、近くによい資格スクールがないこともあるでしょう。通信講座ですと通う必要がないので問題を解決できます。
通学講座の場合、時間になると講座が始まるので多少集中できていなくとも勉強モードに切り替えさせてくれる強制力があるのがメリットです。
もちろん、集中できるかどうかは本人次第ですが、学ぶためによい環境だと言えるでしょう。
ほかも受験生が勉強する姿を見て、「私も頑張ろう!」とやる気になる人も多くいます。独学にはないメリットですね。さらに、受講生同士で情報交換を行うこともあるようです。
資格スクールのデメリット
- お金がかかる
- 【通学講座の場合】時間の都合を資格スクールのカリキュラムに合わせないといけない
先ほども触れましたが、目安として年間100万円ほどを資格スクールの受験料として支払っている人も少なくありません。
通信講座ですと、比較的安く済ませられますが、独学の料金とは比にならないので、躊躇う人も少なくないようです。
また、通学講座の場合、時間の都合を資格スクールのカリキュラムに合わせないといけないのが苦労するところです。税理士試験のために正社員からアルバイトになった人もいます。
税理士資格試験の勉強におすすめの予備校・通信講座3選
この項目では、数ある税理士試験対策予備校・通信講座のなかでも、おすすめ3つを紹介します。

資格の大原と並ぶ知名度・実績を持つのがLEC東京リーガルマインド。
講師とカリキュラムの質の高さに定評があり、1994年からの受験指導歴のある老舗の試験対策講座サービス。
講座受講は通学・通信のどちらも可。どちらの学習スタイルを選んでも、丁寧な学習フォローが受けられるので安心して、勉強ができる環境が整っています。
講座は初学者から上級者、試験直前期まで幅広く用意されており、ご自身の状況に合わせて選ぶことができます。
公式サイト:https://www.lec-jp.com/
資格試験の予備校といえば、大原が頭に浮かぶ人も多いのではないでしょうか。税理士や公認会計士など士業資格から、FPや簿記などの実用的な資格まで幅広く講座を用意しています。
大原の税理士試験に関する実績としては、2019年度は全国官報合格者749名のうち、434名が大原生。官報合格者の半数以上が、大原生となっています。
講座受講は通学・通信どちらでも可能。講座は科目ごとに用意されており、期間や授業レベルに応じて値段が変わります。
公式サイト:https://www.o-hara.jp/course/zeirishi

スタディングはオンライン専門の資格講座サービスです。
スタディングメソッドと呼ばれる独自の法則をもとに、コンテンツや学習システムを開発。短期間かつ効率的な学習がしやすい教材を提供しています。
【スタディングメソッド7つの原則】
短期間で集中的に繰り返すと記憶に定着する
丸暗記ではなくイメージやストーリーを活用すると忘れにくい
得点に結びつくことから勉強する
スキマ時間を生かして勉強する
問題・過去問は無理に解かずに覚えてしまう
試験本番を想定した練習をする
最後まで完走する
引用元:スタディングメソッドとは|スタディング
また受講料の安さもスタディングの魅力の一つです。
公式サイト:https://studying.jp/
独学で税理士を目指す上での5つのポイント
独学で税理士を目指すためには5つのカギがあります。税理士資格に合格したいなら、一度目を通しておいて損はありません。
全く無知なら不合格まで3000時間が必要
全く無知の状態から始めるのなら、合格までに5年がかかり、勉強時間は3000時間に及ぶことを見込んでおくことをおすすめします。
日商簿記検定の1級を持っていたり、会計事務所での勤務経験があったりすると、多少縮められるかと思いますが、決して楽な道のりではありません。
日商簿記検定の2級レベルをクリアしてから
会計学の2科目は必須科目ですので、全員が受験することになります。受験生が多いので、市販教材が多く出回っているので、比較的独学しやすいでしょう。
しかし、基礎知識がないまま税理士向けのテキストを開いてもつまずくだけです。そこで、日商簿記検定の2級の内容は全てクリアしている状況に足固めすることをおすすめします。
そのあと、簿記論と財務諸表論に進むとスムーズでしょう。
資格スクールで教材だけ手に入れるのもアリ
選択科目である税法は市販の教材が少ないです。ネットオークションで出回っていることも多いですが、税法は頻繁に改正があるため古いテキストでは不十分です。
教材だけで購入できる資格スクールもあるので、そちらで揃えたほうが安心ですね。テキスト費用だけでなく、学習内容が充実しているかどうかで判断しましょう。独学では、分かりやすいテキストが相棒になります。
法人税・所得税法・消費税法がおすすめ
税理士試験では科目選びが重要です。そこで、独学の人におすすめしたいのが、法人税法・所得税法・消費税法。ボリュームが多いため避けたくなる気持ちがありますが、初学者が多いためライバルのレベルは比較的低いです。
さらに、法人税法と所得税法の両方を勉強すると、論点が重なる部分があるため、勉強を進めやすいです。
頻繁に改正する情報をキャッチする
税法は頻繁に改正されるので、独学なら自ら情報をキャッチしていかないといけません。
資格スクールでは講師が教えてくれるので、独学の大変なところだと言えるでしょう。税法改正の情報は官報や厚生労働省、経済産業省のホームページなどで確認できます。
まとめ
税理士になりたいと思ったとき、経済的理由や時間的制約によって独学を選択する人もいます。
モチベーションの維持や改正される情報をキャッチしなければいけないといった大変な点がありますが、独学で合格した人もいることを励みしてください。
独学でやり始めたからと言って最後まで独学でやり通す必要もありません。
2科目は独学で、残り3科目は資格スクールで、という選択があってもよいはずです。いま選べる最善の道を選びましょう。