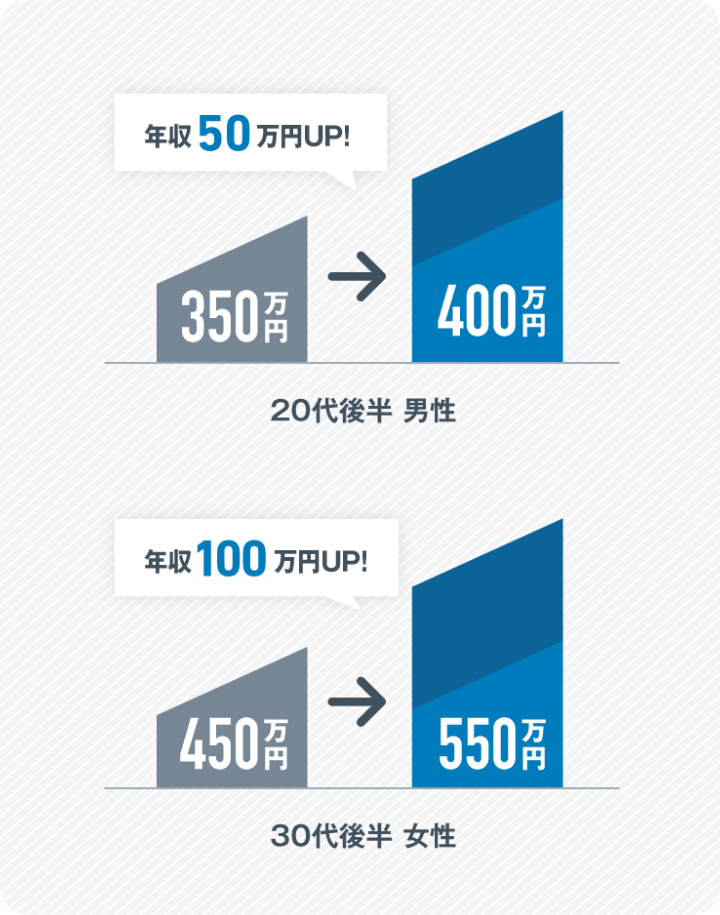「転職したいけど年齢が年齢だしな…」
「転職は20代半ばが限界だってよく聞くし…」
転職を考えてはいるが、年齢というものに壁を感じて、一歩を踏みだせない人も少なくありません。
結論からお伝えすると、年齢によって転職しにくくなることはありますが、『転職が絶対にできない』というような年齢制限はありません。
若い人材が少なくなってきていること、昔と比べて年齢ではなくスキルを見てくれる企業も増えてきていること、そして、厚生労働省による『中途採用』への呼びかけが始まったことなどによって、限界年齢というものがなくなってきたからです。
転職の年齢制限についてよく知りたい方に向けて、この記事では以下のことなどをお伝えしましたので、本記事をぜひご覧ください。
●転職の限界年齢とは
●年齢制限は合法なのか
●年齢制限がある求人に応募したい時は
転職がギリギリ可能な年齢とは|さまざまな説について解説
転職の限界年齢と呼ばれる年齢について解説します。
限界年齢1:28歳
『若い内に専門技術をこれから身につけたい人』は、『転職の限界28歳説』を信じてもよいでしょう。
専門技術を身につけるまでには、2年間程度は必要であること、そして一般に若者としてみなせる限界が『30歳』程度なので、その2年前の『28歳』が注目され、浮上したのが『転職限界年齢28歳説』です。
ちなみに、20代は『探索期』と呼ばれますが、これは自分のスキルや可能性を探す期間のことを言います。
そして、30代は『確立期』と呼ばれ、専門性を確立する期間と言われています。
このような年代の区別からも、『専門性がない状態での転職』は20代後半が限界であることが分かります。
限界年齢2:32歳
限界年齢が32歳という説もありますが、『年功序列』を気にする企業に転職しない限り、気にしなくてもよい説です。
32歳が限界年齢だったのは一昔前まで。以前は日本人には『年功序列』という考え方が一般的だったため、年下の上司なんて状況は存在してはいけないと考えられていました。
そのため、部下が年上になってしまうケースが起きないよう、採用試験の時点で『年齢による落選』を行なっていたのです。
ですが、最近では景気の関係から『年齢による落選』がなくなってきました。
バブルの時は能力のない人でも稼ぐことができましたが、現代ではバブル時ほど景気がよいわけではないので、能力のない人は稼げず、会社の役に立ちません。
今は能力のある人を雇って会社を回していく時代、つまり、能力で人を選ぶ時代になってきていると言えます。
そのため、『年功序列を過敏に気にする企業』自体が珍しくなってきているので、年齢を気にする必要がほとんどないということです。
限界年齢3:35歳
10年ほど前に話題になった『転職限界年齢35歳説』は、まったく気にする必要がありません。
限界年齢が35歳という説は、2006~2007年ごろの転職市場でのブームが影響しています。
当時、1993年から2002年前後の就職氷河期に就職が叶わなかった若手世代を、『第二新卒』という形で改めて採用する会社が多くいました。
企業の人材需要にも上限があるため、若手世代をたくさん採用した分、35歳以上の熟年世代の採用が激減します。
この件をうけて、「35歳以上は転職できないのではないか?」ということを言い出す人がいたため、『転職限界年齢35歳説』が浮上したのです。
逆に言えば、就職氷河期の影響は現代には残っていないので、現代人は『転職限界年齢35歳説』を気にする必要がないということです。
実際に、年々転職者の平均年齢は上がり続け、2020年には35歳以上の転職成功者が28%以上もいます。
つまりは、4人に1人以上の転職成功者が35歳以上となっているのです。
限界年齢4:女性の30歳
30歳を節目に事務職の求人は減りますが、他職種の求人は減らないため、女性の転職する際の限界年齢が30歳というわけではありません。
これまで女性が事務職に就くことが多かったので、限界年齢が30歳という説が生まれたようです。
総合職や専門職ならば、男性と同様に限界年齢はありません。
企業が年齢制限を設ける理由

ここでは、企業が年齢制限を設け、若い人を積極的に採用する理由についてお伝えします。
①将来性があるから
『長期間会社に所属できる人の方が、技術をたくさん身につけて、会社の役に立ってくれるだろう』という将来性の観点から、中年よりも若い人の方が好まれると判断できます。
例えば、同じスキルを持っている2人がいたとしましょう。
その2人はそれぞれ25歳と35歳です。
短い目で見たら、両方とも同じだけの利益を出してくれるように見えますが、長期的な目で見た時、圧倒的な違いが生まれます。
その違いの根源は、働ける残りの年数が10年も違うことです。
25歳は35歳よりも10年間も多く働けるので、10年の間にさらなる技術を身につけて、会社に利益をもたらすことを期待できます。
結果、企業は25歳の人の方を採用するでしょう。
②年上の部下はなるべく避けたいから
年上の部下を作らないように、年齢制限を設けるケースもあります。
仕事中であっても、年上に注意するのは気が引けるでしょう。この気持ちが業務の停滞につながることがあるので、部下は年下の方が理想的です。
そのため、同じスキルを持つ応募者ならば、上司となる年齢よりも年下が好まれる傾向があるようです。
そもそも求人における年齢制限は合法なのか
原則として「求人には年齢制限を設けてはいけない」とあります。
どのような法律で禁止されているのか、また年齢制限を設ける場合どんな条件があるのかについて解説します。
求人応募に年齢制限を禁止する項目がある
2007年6月1日、『雇用対策法』が大きく改正されました。
改正内容は、『募集・採用段階での年齢制限を行わないようにする』といったもので、当時(2007年以前)は当然のように見られた、『30歳以下募集』や『35歳まで』といった年齢制限の記載が、改正後、急速に見られなくなりました。
事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。
【引用: 募集・採用における年齢制限禁止について|厚生労働省 】
年齢制限を禁止する目的
年齢制限の禁止というのは、年齢差別を減らすという目的があったとされています。
年齢差別は倫理的にはもちろんですが、人口減少していく中で生まれたのは、『より多くの人が社会を支えよう』という観点です。年齢で応募を限定してしまうのではなく、個々人の持つ能力、適性を鑑みて募集・採用をしていくことが求められていました。
・年齢制限禁止の義務化は、 個々人の能力、適性を判断して募集・採用していただくことで、一人ひとりにより均等な働く機会が与えられるようにすること を目的としています。
・少子高齢化のなかで、我が国経済の持続的な成長のためには、個々人が年齢ではなくその能力や適性に応じて活躍の場を得られることが重要です。
例外|応募条件に年齢制限を設けていい条件がある
|
◆ 例外となる場合 ◆ |
|
|
例外1 |
定年まで働ける年数を考えると能力発揮が難しい場合 |
|
例外2 |
労働基準法やその他の法令の規定により年齢層の就業が制限されている場合 |
|
例外3-1 |
長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、新卒者などを期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
|
例外3-2 |
技能・ノウハウの引き継ぎの観点から、特定の職種において特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
|
例外3-3 |
芸術・芸能の分野における表現の真実性などの依頼がある場合 |
|
例外3-4 |
60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合 |
例外1の事例として、定年が60歳の会社が、60歳未満の人を募集すること、例外2の事例として、労働基準法第62条の危険有害業務の理由から18歳以上の人を募集することなど、国の施策に沿う形での年齢制限を認めています。
年齢制限を超えてしまっている求人に応募したい場合
手順1:まずは問い合わせる
要項に年齢制限がある場合、確認を取らずに送付すると『非常識』と捉えられてしまう恐れがあります。
少し手間ではありますが、『年齢制限をオーバーしていても大丈夫かどうか』を先方の採用担当部署に電話で問い合わせましょう。
問い合わせの際、先方からの質疑応答があるかもしれませんので、ある程度心の準備をしておくと、スムーズに回答ができます。
認めてもらえた場合には、必ず感謝の意を告げましょう。
手順2:履歴書で熱意を表す
次に履歴書を書く作業に入りますが、採用担当の方に「募集年齢からは超えてしまっているが、この人ならば採用したい」と思ってもらえるように、自分のアピールポイントをしっかり書きましょう。
また、以下のポイントを意識するとよいでしょう。
- 知識や技術に対して積極的で、変化に対応する能力があること
- いままでの経験を活かして先方の戦力になること
- コミュニケーションが取れ、いろんな人と仕事していけること
さらに、実績があれば積極的に書き込んでいきましょう。
【関連記事】
▶ 転職用の履歴書のフォーマットと作成する際のポイントまとめ
▶ 転職の履歴書|書き方の基本と注意するべき5つのポイント
▶ あなたの自己PRは大丈夫?転職における面接テクニック
年齢制限のハンデがあっても有利に転職できるケース
年齢制限に引っ掛かっている状況でも、有利に転職できるケースをご紹介します。
①前の職場で実績がある
前の職場で『専門性』と『再現性』を身につけていると有利に働きます。
『専門性』とは、その業務における深い知識・技術のことを言います。
任されていた仕事において実績を3年間出し続けていれば、どこでも専門性があるとみなされるでしょう。
3年というのは目安ですが、早々に辞めてしまうと身についていないと思われてしまうかもしれません。
『再現性』とは、繰り返し結果のある実績を実現できるかどうかのことを言います。例えば1年目で実績を出していたとしても、「運よく結果を出した可能性がある」と思われることもありますが、3年間程度繰り返し実績を出し続けることができれば、『再現性』があるという評価の対象になるでしょう。
②コミュニケーションが取れる
同期の中でも年齢が高くなってしまったり、上司が年下になったり。
高齢での転職の際には、カドが立つ状況が少なくないでしょう。
そのため、高齢の転職者には、その環境で周囲とうまくコミュニケーションが取れることが求められます。
さらに、年下の手本となり得る人物ならば、有利に働くでしょう。
③転職に明確な理由がある(やりたいことがある)
会社にとって自分がどれほどの価値があるか伝えられる必要があります。
会社に利益をもたらす見込みのある人材ならば、年齢を超えていても採用する価値があります。
自分がどれほど有益な人材かを伝えることによって有利に働くことでしょう。
まとめ|転職する時に壁になるほどの年齢制限はない
現在(2021年)は、転職する若い人材自体が少なくなってきている上に、「年齢制限を極力控えるように」と厚生労働省が呼び掛けています。
転職時に年齢がネックになると感じる必要はありません。
もし希望の職場があるのであれば、一度申し込んでみてはいかがでしょうか?
本記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。
- 新着コラム
- 人気コラム
- おすすめコラム