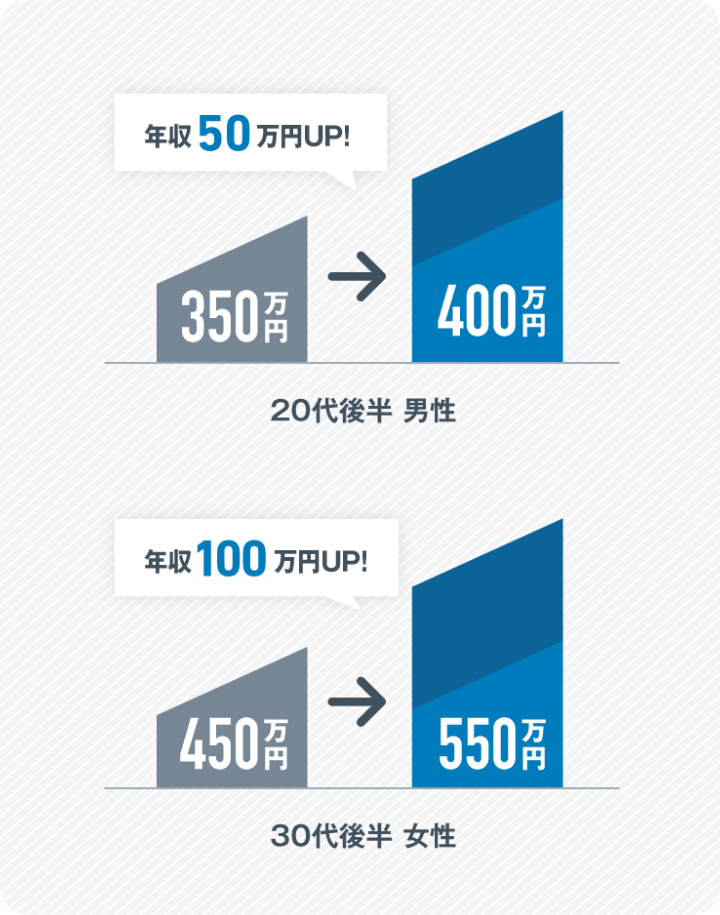2016年、キャリアコンサルタントは国家資格となりました。
国は2024年までにキャリアコンサルタントを10万人まで増やしたいと考えており、養成を積極的に推進しています。
取得を考えている人にとって、難易度や受験資格については一番の関心事ですよね。
ここではその具体的な解説と、あわせて効果的な勉強方法についても説明していきます。
キャリアコンサルタントとはどのような仕事?
キャリアコンサルタントとは、その人にとって望ましい職業選択やキャリアの描けるように支援する専門家のことです。
相談にきた人(クライエント)の話に真摯に耳を傾け、抱えている悩みや価値観やスキルなどを丁寧に聞き取りながら、その人が今後の人生をポジティブに行動できるようサポートしていきます。
「あなたにはこれが向いている」と助言をする仕事であるとイメージされがちですが、それは大きな誤解です。
相談者がまだ気付いていない潜在的な気持ちや考えを一緒に整理し、相談者自身に今後どうすべきか考え抜いてもらうことを手助けする仕事です。
難易度高め?国家資格であるキャリアコンサルタントの合格率
キャリアコンサルタント国家資格は学科試験と実技面接試験の両方に合格する必要があります。
2020年に3月に実施された第14回キャリアコンサルタント試験における合格率は55.3%(※)でした。2人に1人は合格する試験なので、難易度はそれほど高くないと言えるでしょう。
※学科、実技面接試験同時受験者2771名のうち、1533名が合格。(2つの試験機関合算値)
|
受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
|
|
学科、実技試験同時受験者 |
2,771 人 |
1,533 人 |
55.3% |
|
申込者数 |
受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
|
|
学科試験 |
3,458 人 |
3,329 人 |
2,237 人 |
67.2% |
|
実技試験 |
3,720 人 |
3,649 人 |
2,407 人 |
66.0% |
参考:厚生労働省|第14回キャリアコンサルタント試験結果の概要
学科合格率は67.2%
学科合格率は67.2%で、受験者3329名のうち2237名が合格しています。
学科試験は実技面接試験と比較すると、回によって難易度が異なり合格率が変動します。おおむね平均は50%~60%あたりですが、過去には21.3%(第4回)や77.8%(第1回)という時もありました。
学科試験は1問が4択のマークシート方式で全部で50問あります。試験時間は100分で、100点満点のうち70点が合格ラインです。
実技面接合格率は66.0%
実技面接合格率は66.0%で受験者3649名のうち2407名が合格しています。
実技面接試験には論述試験と面接(ロールプレイ)試験の2つで構成されています。150点満点のうち90点以上が合格になります。これまで実施されたすべての回で合格率は60%以上を保っています。
なお、過去にキャリアコンサルタント試験の受験歴があり、学科試験又は実技面接試験においてどちらか片方に合格している場合は、次回からその試験のみ免除になります。
受験団体別|キャリアコンサルタント試験の難易度は変わる?
実は、キャリアコンサルタントの国家試験には2つの実施機関があります。
- 日本キャリア開発協会(JCDA)
- 特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会(CC協議会)
この2つは何が異なるのでしょうか。どちらが受かりやすいといった偏りはあるのでしょうか。
日本キャリア開発協会(JCDA)とキャリアコンサルティング協会の違い
2つの団体はどのような違いがあるのでしょうか。
日本キャリア開発協会(JCDA)とは?
アメリカのキャリアカウンセリングを最初に導入した団体です。クライエントの話す内容から「経験の再現」と「意味の出現」を行い、この過程を通してクライエント自身の内面の成長を目指すという独自の理論(経験代謝)を発展させたことで有名です。
キャリアコンサルティング協会とは?
キャリアコンサルタントを養成する複数の団体から構成されています。クライエントが自分の適性・志向を自己分析し、自律的にキャリア形成していくことを目的とした団体です。
キャリアコンサルタントになるための要件として、基本的態度、関係構築力、問題把握力、展開力の修得を求めています。
JCDAとキャリ協で合格率が違う理由
試験は2団体ともに同一日程で実施されます。学科試験については、共通の問題を使用します。しかし、実技面接試験(ロールプレイング)では2団体の評価基準が微妙に異なるため、合格率に差がでているのが実態です。
それぞれ下記の2点の観点で採点されます。
1:「主訴・問題の把握」「具体的展開」「傾聴」
|
日本キャリア開発協会(JCDA):合格率65.3%(2020年3月第14回) |
2:「態度」「展開」「自己評価」
|
特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会(CC協議会): 合格率66.6%(同) |
どちらかで受験した方が受かりやすいのか?
どちらで受験した方が自分にとってよいのか結論を出すためには、自分のタイプと、どの養成講座経由で受験するかによって慎重に見極める必要があります。
自分のカウセリングタイプから決める
クライエントの話をじっくりと傾聴しながら、本人の自発的な気付きを促すような丁寧なカウンセリングを得意とする人は、JCDAで実技面接を受けるとよいでしょう。
それに対し、問題解決にむけて認知の変化、行動変容、意欲の変化を積極的に促すような関わり方を得意とする人はCC協議会の方が合っているでしょう。
講習(養成スクール)で決める
講習(養成スクール)修了により受験資格を得る人は、その養成講座がどちら寄りの内容なのかで決めるのもひとつの手です。例えばマンパワーの主催する講習ではJCDAの理論をベースとした内容になっているので、JCDAでの受験がおすすめです。
実務経験受験の方の場合
実務経験で受験資格を得た人は、どちらかというとCC協議会の方をおすすめします。JCDAの方が合格率が低めであるためです。
どちらを選ぶかはその都度決められる
受験団体は、受験するその都度変更できます。不合格が続くような場合は、自分と試験の特徴との相性をよく踏まえたうえで、受験団体の変更を検討しましょう。
キャリアコンサルタント資格を取得する3つのメリット
キャリアコンサルタント資格がなくとも、友人や同僚・部下のキャリア相談にのることは可能です。実際、転職エージェントには、資格をもたずにキャリアアドバイスを実施している人もいます。
あえて資格を取得することで、どのようなメリットを享受できるのでしょうか。
1:支援レベルが向上する
キャリアカウセリングについての理論や専門知識を体系的に学ぶことで、支援レベルは各段にあがります。ヒアリング技術や関わり方の手法など、クライエントに合わせたバリエーションを取得できるので、自己流のやり方から脱却できます。
2:交流の場や継続学習の機会が得られる
合格者同士(同期)のネットワークをもつことができ、情報交換が可能です。また、研究会・国家資格更新講習・キャリアアップ研修などが用意されており、継続的にスキルアップできる機会が得られます。
3:仕事を得ることができる
資格を取得すると、『キャリコンサーチ』というWebサービスに登録できます。これは「キャリアコンサルタント」と「キャリアコンサルタントを探したい企業担当者や個人等」をつなぐサービスで、就職支援や転職支援を行う企業などからスカウトを受けられる仕組みです。
キャリアコンサルタントが活躍できる場所
資格保持者の多くは、下記のような場でキャリアコンサルティング活動を行っています。
- 人事/教育/人材開発部門
- 転職支援を行う人材紹介会社、派遣会社
- 再就職支援サービス運営企業
- 学校内でキャリア教育を担当する部署
- ハローワークなどの公的機関
副業や独立も可能
組織に属さなくても、キャリアコンサルタントとして独立して就職支援や転職支援をすることが可能です。またクラウドソーシングなどを使って、副業の形でコンサルタント業務に従事することもできます。
日常生活にも活かせる
キャリアコンサルタントという役職でなくとも、日常の随所でキャリアコンサルタントとしてのスキルを活かすことができます。
例えば上司が部下のキャリアについて助言する際や、家庭での子育て、地域活動・ボランティアでも知識を活用できるでしょう。
なぜいまキャリアコンサルタント資格が注目されているのか
人生100年時代の到来とともに、人生における就業時間が長期化しようとしています。既に定年を70歳とする法案も整備されようとしており、そうなれば人は50年ものあいだ働き続けることになります。それに伴って、働き方もますます多様化していくことでしょう。
長い人生のあいだ、人は何度もキャリア選択の岐路に立つことが想定されます。そうした背景から、自律的なキャリア選択について専門的にサポートできるプロがいま求められています。
キャリアコンサルタントに向いている人は?
キャリア形成支援とは、キャリアコンサルタントが「あなたは○○の仕事に向いている」と判断を下して、一方的に特定の解決方法を提示することとは少し違います。
相談者が自分で自分の内面に目を向け、抱えている悩みに対し自分自身で納得する回答を見つけていくプロセスを支援する仕事です。
人生経験豊富だからといって、自分の価値観や考えを一方的にアドバイスする人がいますが、そういう人はあまり向いていません。
どちらかというと、下記のようなタイプの人が向いているといえます。
- 傾聴力、ヒアリング力がある人、
- 相手のペースに合わせた会話の進行ができる人
- 相手の気持ちに寄り添える、共感力の高い人
- 他人の力になりたいという、高いホスピタリティをもっている人
- 雇用や働き方関連のニュースに関心がある人
キャリアコンサルタント試験合格までにやるべきこと
まずは受験資格を得ましょう。3年の実務経験がなければ指定の講習(養成スクール)に通いながら勉強していく形になります。
どのくらい勉強時間を確保すべき?
講習の実施機関によって幅はあるものの、通信・通学講座を合わせると、合計140時間~200時間ほどのカリキュラムが組まれています。
プラスしてこの他に自己学習が必要となりますが、その勉強時間は人によって大きく異なります。
既に仕事(実務)でキャリア支援業務を行っている人は、学習スピードも早く、集中して1~2ヵ月程度勉強すれば過去問である程度の得点を得られるレベルに到達します。
一方で全く経験のない人は2~4ヵ月程度の学習期間を要するでしょう。
どのような勉強・試験対策をするのが良い?
キャリアコンサルタント国家試験は2名に1名が合格できる試験です。毎回、過去の問題と似た内容が出題されますので、対策が立てやすい試験と言えるでしょう。
キャリアコンサルタント試験は学科・実技面接ともに過去問が公開されていますので、最終的には過去問で合格点をクリアできるレベルに仕上げることを目標としましょう。
学科試験はテキストと問題集を繰り返し解くことで、得点を伸ばせます。一方、実技面接はロープレの練習が不可欠になるので、独学では限界があります。
一緒に練習する仲間が必要です。講習で一緒になった人たちと早めに関係性を築いておくとよいでしょう。
おすすめの通信講座や資格スクールは?
キャリアコンサルタント試験の受験要件のひとつとなる、厚生労働大臣が認定した講習については2020年4月現在、21の講習が認定されています。
どのスクールの講習でも、きちんと修了すれば受験資格を得られますが、受講費用や開催場所、講習の内容についてはそれぞれ違いがあります。
「実践練習が多い」「少人数制をとっている」「地方で開講している」など各社さまざまな特色を打ち出していますので、可能であれば、いくつか事前説明会(相談会)に参加してから決めるようにしましょう。
試験合格後の流れ
学科試験と実技面接試験の両方に合格し、キャリアコンサルタント名簿に登録することにより「キャリアコンサルタント」として名乗ることができます。キャリアコンサルタントは5年ごとに更新を行い、最新の知識・技能を身につける必要があります。
まとめ
キャリアコンサルタントが注目されている理由、具体的な業務内容を踏まえ、合格率、受験方法について解説してきました。キャリアコンサルタント試験の難易度はそこまで高くなく、過去問でしっかり準備をすれば合格しやすい試験です。
講習に通う場合でも通学期間も含め最短で半年で合格することが可能です。
試験も年三回あり、仮に初回のチャレンジが不合格に終わったとしても、すぐに再チャレンジ可能ですので、あきらめずに頑張ってください。
転職・人材業界に深く関わるディレクターが『今の職場に不満があり、転職を考え始めた方』や『転職活動の進め方がわからない方』へ、最高の転職を実現できる情報提供を目指している。
本記事はキャリズムを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※キャリズムに掲載される記事は転職エージェントが執筆したものではありません。
- 新着コラム
- 人気コラム
- おすすめコラム