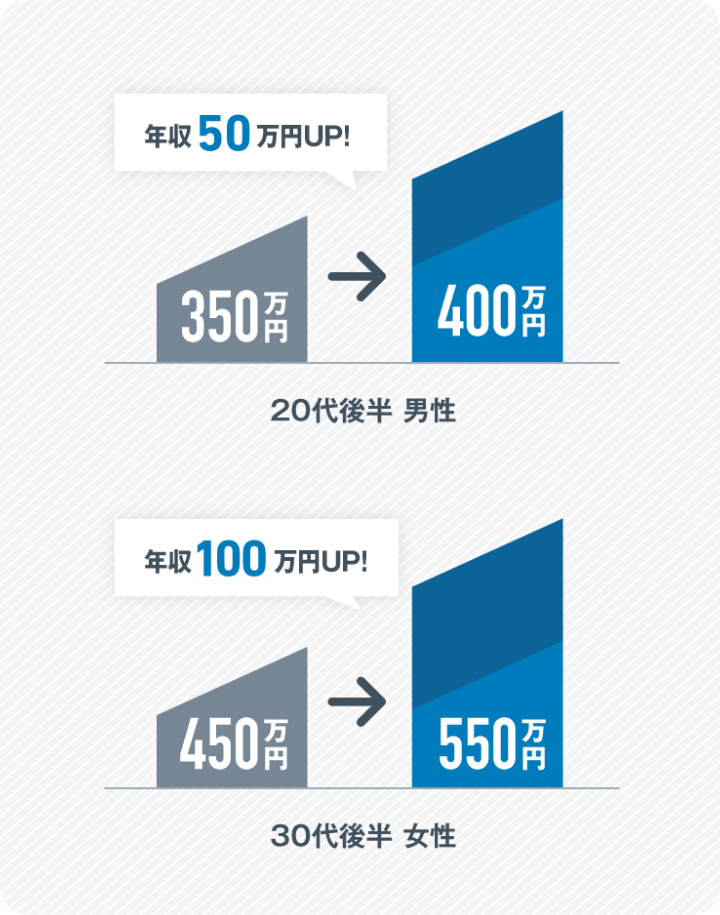働き方が多様化しているとはいえ、仕事と生活を完全に分離させられる人はいないでしょう。働くことは生きることでもあります。
キャリアコンサルタントとは、相談者(クライエント)が「望ましいと感じるキャリア開発とはどのようなものなのか」を一緒になって考え、そこに到達するまでの支援を行う専門家です。
2016年に国家資格になってから大きく注目されはじめ、年々養成スクールの数も増えています。
この記事では、気になる受験資格から試験の内容、難易度、取得後の活躍場所までキャリアコンサルタントに関する情報を全てまとめていきます。
キャリアコンサルタントになるまでの流れ
キャリアコンサルタントになるには、どのような手順を踏むとよいのでしょうか。
要約すると3つのフェーズがあります。
- フェーズ①:受験資格を満たす
- フェーズ②:試験(学科と実技面接両方)に合格する
- フェーズ③:キャリアコンサルタント名簿に登録する
受験資格を得るためには実務経験もしくは講習受講が必須 ←「相談実務があることが前提」から変更致しました。
キャリアコンサルタントを受験する際、性別・年齢・学歴は一切問われません。下記の受験資格のうち、どれかひとつを満たしていれば誰でも受験できます。
- 厚生労働大臣が認定する講習の課程を修了した方
- 労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上のいずれかに関する相談
に関し3年以上の経験を有する方
- 技能検定キャリアコンサルティング職種の学科試験又は実技面接試験に合格した方
- 2016年3月迄に実施されていたキャリア・コンサルタント能力評価試験の受験資格
である養成講座を修了した方(2016年4月から5年間有効)
実務経験とは
「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上のいずれかに関する相談に関し3年以上の経験を有する方」とは具体的にどのような内容を指すのでしょうか。
基本的には次の3点いずれも満たしていることが原則です。
- キャリアコンサルティングによる支援対象者が、「労働者」であること。
支援対象者が現職中・求職中かは問わない。また学卒就職希望者も含む。 - 相談の内容・目的が職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上に関するものであること。
- キャリアコンサルティングが一対一もしくは、少人数グループワークの運営等の経験があること。情報提供のみや授業・訓練は含まない。
分かりやすくいうと、大学でのキャリア支援業務、ハローワークや民間の紹介会社で個人向けの転職支援をしていた人などが該当します。
実務経験として認定されるためには、出願時に定められた様式(実務経験証明書)に記入して提出することが求められます。
実務経験がない場合は養成講習を受講する
3年以上の実務経験がない人は、厚生労働大臣が認定する講習を受ければ受験資格を得られます。
2020年4月の時点で認定されている講習は21。実施機関、開設時期・エリア、料金がそれぞれ異なります。講習には通学型と通学&通信型の2種類あり、通信のみという講習はありません。
実施機関によっては一部の大都市エリアのみでしか開催していないところもあるので、自宅近くで開校されているかどうか、講習選択時に注意が必要です。
料金についても各機関で幅があるので、講座のカリキュラムや内容と共に比較検討が必要です。
養成講習の期間は?
講習の実施機関によって幅はあるものの、通信・通学両方を合わせると、合計140時間~200時間ほどのカリキュラムが組まれています。通学は10~12日程度の日程が一般的です。
費用はかかる?
実施機関によって約24万円~44万円と幅があります。ほとんどの講座が専門実践教育訓練給付金の対象講座になっており、受給資格を満たしていれば最大で70%の補助が受けられます。
国家試験を受けて資格を取得する
受験資格を得られたら、さっそく試験の申込み(受験申請)をしましょう。
試験日は?
試験は学科(筆記)試験と実技試験から構成されており、3月・6月・11月の年3回実施されます。講習を修了したのち、何年以内に受験しないとならないといった決まりは特に設けられていません。自分の状況に合わせて、どの回の試験をいつ受験しても大丈夫です。
試験の難易度は?
学科試験は1問が4択のマークシート方式で全部で50問あります。試験時間は100分で、100点満点のうち70点が合格ラインです。一方、実技試験の方は150点満点のうち90点以上が合格になります。
2020年に3月に実施された第14回キャリアコンサルタント試験における合格率は55.3%(※)でした。2名に1名合格している状況です。
※学科、実技面接試験同時受験者2771名のうち、1533名が合格。2つの試験機関合算値)
|
受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
|
|
学科、実技試験同時受験者 |
2,771 人 |
1,533 人 |
55.3% |
|
申込者数 |
受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
|
|
学科試験 |
3,458 人 |
3,329 人 |
2,237 人 |
67.2% |
|
実技試験 |
3,720 人 |
3,649 人 |
2,407 人 |
66.0% |
参考:厚生労働省|第14回キャリアコンサルタント試験結果の概要
受験費用は?
受験費用は学科試験が8,900円、実技試験が29,900円です。受験申し込み後はいかなる理由があっても受験料の返還をしてもらうことはできません。
次回以降の試験への振替もできないので注意が必要です。
スクールに通うべき?
実務経験があればスクール(養成講習)に通う必要はなく、独学で勉強可能です。受験資格を得るための厚生労働大臣に認可された養成講習ではなく、試験対策講座に特化した個人塾などもありますので、ネットで探して申し込むのもひとつの方法でしょう。
試験合格後はキャリアコンサルタント登録
試験に合格しただけではキャリアコンサルタントを名乗ることはできません。合格後キャリアコンサルタント名簿に登録して初めて名刺などに記載できます。登録の手続きは特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会にて行います。
また、登録後は『キャリコンサーチ』というWebサービスを利用できます。これは「キャリアコンサルタント」と「キャリアコンサルタントを探したい企業担当者や個人等」をつなぐサービスで、就職支援や転職支援を行う企業などからスカウトを受けられる仕組みです。
登録費用は?
登録申請には以下の費用がかかります。
- 登録免許税:9,000円
- 登録手数料:8,000円
登録申請後1.5~2.5ヵ月程度で「キャリアコンサルタント登録証」が交付されます。
キャリアコンサルティング技能士へのチャレンジも
より高い技能を身につけたい人には、キャリアコンサルティング技能士(1級・2級)の受験を視野にいれてみましょう。
2級は"熟練レベル"、1級は"教育者レベル"として評価されています。キャリアコンサルタント資格を取得ののち、一定の実務経験を積むことで受験資格が得られます。
2級の受験資格は最低でも3年の実務経験が必要なので、人によっては長期戦になるかもしれませんが、難易度が高いだけにプロのコンサルタントとして成長したい人にはおすすめの資格です。
キャリアコンサルタントの年収は?
キャリアコンサルタント保持者の年収は、活動形態によって異なります。
2017年の調査(※)によると、例えば一般企業に雇用されている人は「400~600 万円未満」「600~800 万円未満」「800 万円以上」の年収価格帯にそれぞれ20%以上分布しています。

これに対し、学校・教育機関、需給調整機関、地域、その他等では「200万円未満」「200~400 万円未満」が多い状況です。

また、雇用形態によっても差があり、正社員では「400~600 万円未満」「600~800 万円未満」「800 万円以上」が多い一方で、非正規社員では「200 万円未満」「200~400 万円が中心となります。

フリー・自営およびボランティアの人たちは、「200万円未満」の層が相対的に多い状況になっています。安定的に高収入を得るなら民間の一般企業を選んだ方が良いと言えるでしょう。
参考:労働政策研究報告書No.200『キャリアコンサルタント登録者の活動状況等に関する調査』
キャリアコンサルタントの仕事内容・役割とは?
キャリアコンサルタントとは、キャリアコンサルティングを通じて相談者(クライエント)のよりよいキャリア支援するエキスパートです。
クライエントはキャリアコンサルティングを通じて、自分の志向や価値観、適性やスキルを認識し、自分に合ったキャリアを主体的に選択できるようになります。
代表的なキャリアコンサルタントの支援事例を5つ挙げます。
大学の就職課で、就職指導のサポートをする
大学や専門学校のキャリアセンターに在籍し、就職支援や進路相談を担当します。
これまで一度も働いたことのない学生にとって、自己分析や企業研究などは初めて体験するワークであり、どのように自分に合った企業を見つければいいのか悩む学生も数多くいます。
学生ひとりひとりの気持ちを丁寧にヒアリングし、インターンシップや適性検査受検案内、求人の紹介など様々な選択肢を明示するのが主な役割です。
民間の人材紹介会社で転職支援を行う
人生100年時代と言われるようになり就業期間が伸びていく中、転職すること自体は珍しくなくなりました。2019年の転職者数は351万人と過去最多を更新しており、なかでもより良い条件の仕事を探すために前職を離職した転職者が特に増加しているといいます(※)。
- 「これまでの職歴でどのような経験を積んできたか」
- 「新たなステージでどのような成長を遂げたいか」など
相談者が自ら考えを整理し、言語化できるような手助けを積極的に行っていきます。その上で、自社で保有している求人の中から最適と思われる案件をいくつか提案し、内定となるよう親身なサポートを行っていきます。
ハローワークで再就職支援業務に携わる
地域の雇用の需給調整機関として重要な役割を果たすハローワーク。キャリアコンサルタントには、その地域にある求人の特性を把握することと、相談者の適性・志向性を理解すること両方が求められます。
企業と相談者双方の傾向を理解することで、マッチング精度が向上し、ミスマッチを防ぐ役割を担います。
人事課でキャリア支援制度を立案する
自社の経営戦略に合わせて、戦力となる人材を中長期的にどのように育成すべきかを具体的な計画に落とし込みます。
研修制度や資格取得制度などを整備し、社員がモチベーションを維持できるように、報酬や処遇に反映させる人事制度の企画・運営もあわせてすすめていきます。
管理職として部下のキャリア開発を行う
部下のキャリア形成支援は、上司にとって重要なミッションです。部下のタイプに合わせて、具体的なスキルアップ方法を適切なタイミングでアドバイスすることが求められます。
そのためには日ごろから部下の言動をよく観察して、部下の興味・関心がどこにあるのかを把握していなければなりません。
部下の才能が開花しそうな部署や役職を明示し、新しいチャレンジをするきっかけ作りを行います。
キャリアコンサルタントの主な就職・転職先
キャリアコンサルタントが活躍する場所は多岐にわたります。前項であげた、「企業」「学校・教育機関」「ハローワーク、転職・再就職支援」の他にも、次のような職場で活躍しています。
- 福祉施設:障がい者の就労支援・職業相談
- 医療機関:患者さんの社会復帰・職場復帰の支援
- 刑務所や少年院:出所後の自立支援・就職支援
- 市役所などの行政機関:生活保護受給者の就労支援
- NPO法人:依存症の人の自立支援・就職支援
ここに挙げたのはほんの一例ですが、一般の民間企業や教育現場だけでなく、福祉や医療の現場でも、「キャリア」という視点で支援していくプロが必要であることがわかります。
キャリアコンサルタントは多様な役割を果たす、社会的に強いニーズのある職業なのです。
キャリアコンサルタント資格を取るための資格スクール
キャリアコンサルタント試験の受験要件のひとつとなる、厚生労働大臣が認定した講習については2020年4月現在、21の講習が認定されています。
どのスクールの講習でも、きちんと修了すれば受験資格を得られますが、受講費用や開催場所、講習の内容についてはそれぞれ違いがあります。
「実践練習が多い」「少人数制をとっている」「地方で開講している」など各社さまざまな特色を打ち出していますので、情報収集をしながら、自分の状況に合ったスクールを選ぶようにしましょう。
ここでは、カリキュラムの充実度や学びやすさなどの観点から5つのスクールを厳選し、紹介をしていきます。スクール選びの参考にしてみてください。
特定非営利活動法人キャリアカウンセリング協会
(講習名:GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラム)
特定非営利活動法人キャリアカウンセリング協会が主催するGCDFというトレーニングプログラムでは、米国発祥の国際的資格を取得することができます。
特徴
GCDFは米国CCE,Inc認定の国際的キャリアカウンセラー資格です。日本だけでなく、アメリカ、カナダ、中国、韓国など世界16地域が採用しており、海外でキャリア支援に就く時にも役立ちます。
キャリアコンサルタントが国家資格になる前から、講座の質の高さには定評があったGCDF。ひとクラス定員18名と他の講習よりも少人数制をとっていることや、通学を12日間と長めに設定していることからも、座学よりも実践に重きを置いていることがわかります。
もちろん資格取得後の交流会や勉強会・研修にも力を入れています。
実施回数は年間52回で4月~3月、10月を除き毎月開講していますが、開催場所が東京、埼玉、神奈川、愛知、大阪、福岡のみであり、このエリア以外の居住者にとっては通いにくいのが難点です。
ただ、中には遠方から新幹線などで移動し、前泊して通う受講生もいるとのことです。
受講費用
396,000円※受講料・テキスト代含む /専門実践教育訓練給付金対象
日本マンパワー
(講習名:キャリアコンサルタント養成講座(総合))
日本マンパワーは、日本で最初にキャリアカウンセラー(CDA)を養成する講座を開いたスクールです。業界の先駆者と言ってもよい存在で、これまで企業や教育機関における数多くのキャリア支援担当者を輩出してきました。
特徴
日本マンパワーの魅力はなんといっても、講座開設拠点が多いことです。首都圏や大阪などの大都市圏はもちろんのこと、北は札幌、南は沖縄まで全国30以上の都市で開催されています。地方エリア在住者にとっては、移動時間や交通費を押さえられるので、大きなメリットとなるでしょう。
受講時間は通学96時間、通信が通信90時間。2つ合わせて186時間という長さは、他講習と比べると長めで、じっくり学びたい人におすすめです。受講生に社会人が多いことを考慮し、急な予定変更などに対応するため、振替受講などのシステムを整えています。
また、参考書や添削などの試験対策オプション講座が充実している点も特長のひとつです。
受講費用
374,000円 /専門実践教育訓練給付金対象
ヒューマンアカデミー
(講習名:キャリアコンサルタント養成講座)
社会人向けの教育講座を多数開設しているヒューマンアカデミー。全国各地に自社教室をもっており、交通アクセスのよい場所に立地しています。
公式サイト:https://ha.athuman.com/
特徴
日本マンパワーにつぐ規模で、全国各地に講座を開設しています。他にはない独自のシステムとして、転校・休学制度を設けています。途中で転勤になっても新たな土地で受講を継続することができる他、事情があって休校したい時には最長一年まで休学が可能です。
ヒューマンアカデミーの最大の特徴は、グループ内に人材サービス会社(ヒューマンリソシア)を抱えていること。資格取得後に転職を検討している場合には、求人票をいつでも閲覧でき、求人応募のサポートも受けられます。
受講費用
302,500円※入学金・教材費は別途 /専門実践教育訓練給付金対象
公式サイト:https://ha.athuman.com/
LEC東京リーガルマインド
(講習名:LEC東京リーガルマインドキャリアコンサルタント養成講座)
法律関連の資格や国家一種公務員など難関資格に対応するイメージが強いLEC。既に別の資格講座を受講している場合には、受講料の割引制度があります。
公式サイト:https://online.lec-jp.com/
特徴
LECには「おためしWeb受講制度」なるものがあります。キャリアコンサルタント資格に興味はあるが、具体的にどんな勉強をするのかをまず知りたいという人向けのミニ講座です。
実際の講習内容の一部が無料でWeb視聴できるので、内容のレベルや雰囲気を確認してから申し込みできます。
LECの特徴は通信教育が充実していることです。一般的な添削課題他に、知識確認テスト100問や講師のレクチャー動画(約18時間)視聴できるなど、LECならではのコンテンツを揃えています。
受講費用
一般価格302,500円(税込)※受講料・テキスト代含む (各種割引制度あり)/専門実践教育訓練給付金対象講座
公式サイト:https://online.lec-jp.com/
リカレントキャリアデザインスクール
(講習名:キャリアコンサルタント養成講座/キャリアコンサルタント養成ライブ通信講座)
リカレントだけが唯一、全過程通学のみの講習を設けています。都市圏のみの開設にはなりますが、自宅学習に苦手意識がある方におすすめしたいスクールです。
特徴
リカレントには通学のみの講習と、通学通信の両方を実施する講習の2種類があります。全過程通学のみの講習では、150時間のカリキュラムが組まれていて、自宅学習ではなかなか身に付きにくいカウンセリングスキルの取得に重きを置いています。
そのため、他のどの講習よりもロールプレイングやグループワークが多めになっており、実践的な内容が多く含まれているのが特徴です。
講師がクラス担任も担っているので、学習をすすめていくうえでの疑問点や不安点について相談できる他、専任のキャリアコンサルタントから資格取得後の就職についてもアドバイスを受けられます。
受講費用
通学のみの講座:437,800円※入会金・教材費は別途 /専門実践教育訓練給付金対象
通学+通信:360,800円※入会金・教材費は別途 /専門実践教育訓練給付金対象
現役キャリアコンサルタントに聞く!なるために大切なこと
大手人材紹介会社でキャリアコンサルタントを務める女性の事例です。
実際にどんな業務をされていますか?
20代~40代前半の個人の方向けの転職支援に携わっています。仕事に対する価値観や、将来どうありたいかという希望をしっかりとヒアリングした上で、実現可能な選択肢をご提案するのがミッションです。
|
【仕事の流れ】 |
|
(1)カウンセリング・求⼈紹介:転職理由や、今後のキャリアプランなど細かくヒアリングをし、自己分析や希望条件の整理をお手伝いします。その後、相談者にあった求人を提案します。 (2)応募書類の添削や⾯接対策の実施:合格率を高めるために、職務経歴書の添削や面接練習を行います。 (3)内定時の条件交渉:相談者の意思を確認しながら入社日や年収などの条件交渉を行います。 (4)退職交渉フォロー/⼊社前後フォロー:現職を円満退職できるように退職交渉のフォローや、入社後の相談に応じます。 |
どんな人が向いている?
高いヒアリング力とホスピタリティを持つ人です。相談者のタイプは様々で、流暢に自分の気持を語れる人もいれば、ひどく無口な人もいます。
相手のタイプやペースに合わせて、寄り添い方やヒアリング方法を変えられるコンサルタントは、相談者と信頼関係を構築する能力にも長けています。
じっくりかけて、相談者自身が気付いていない強みや魅力を上手に引き出すことができると、相談者も前向きな一歩を踏み出しやすく、意欲的に転職活動をすすめることができます。
仕事をする上で大切なことは?
画一的な支援ではなく、その人にあった個別性の高いサービスメニューを用意するようにしています。
新卒の就職活動は同学年であれば皆同じ時期に活動しますが、転職のタイミングは人それぞれです。
一人で転職活動を始めると、自己分析のやり方から求人情報の集め方や面接の突破方法など、分からないことだらけで前に進まないもの。
その人の年齢・スキルなどの状況によって今後の選択肢が異なるので、その人に合った情報提供を行い、前向きでポジティブな一歩が踏み出せるお手伝いをしています。
まとめ
キャリアコンサルタントになるための方法について解説してきました。基本的には相談者と1対1のコミュニケーションをとるため、相手の話に真摯に耳を傾け、共感できる人が向いています。
受験資格は実務経験がなくとも、指定の講習を受講すれば得られます。受験者の2名に1名が合格しているレベル感からみると、難易度が高いとはいえず、チャレンジしやすい国家資格ともいえるでしょう。
働き方が変化し続けている昨今、キャリア支援を必要とする場面は増えています。今後さらなるニーズが高まると想定されますので、興味のある人は是非挑戦してみましょう。
転職・人材業界に深く関わるディレクターが『今の職場に不満があり、転職を考え始めた方』や『転職活動の進め方がわからない方』へ、最高の転職を実現できる情報提供を目指している。
本記事はキャリズムを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※キャリズムに掲載される記事は転職エージェントが執筆したものではありません。
- 新着コラム
- 人気コラム
- おすすめコラム