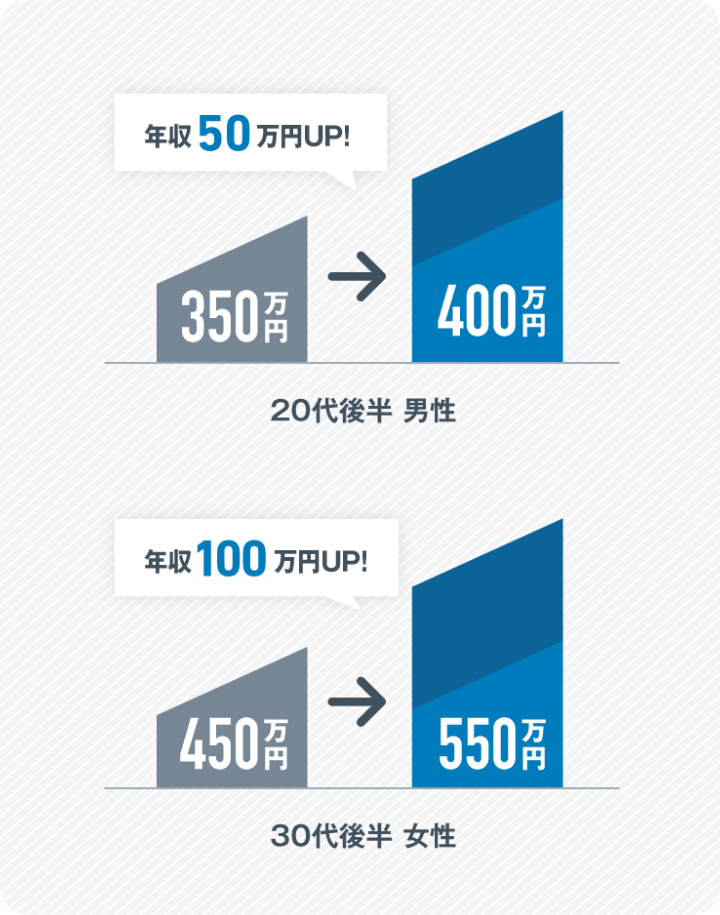就活を意識し始めると、やれ自己分析だの、やれグループワークだの、いろんな言葉が飛び交います。
そして、その中の一つが、「業界研究」でしょう。しかし、結局何をどうすればよいのか不透明になりがちです。
今回は、業界研究のやり方やチェックすべきポイントなどをご紹介しましょう。
就活や転職活動で業界研究をやったほうが良い理由
就活や転職活動では、業界研究をやったほうが良い理由があります。端的にいうと、「自分に合った仕事探し」をするために必要なのです。
就活や転職活動が上手くいかないと、ついつい内定をもらうことがゴールになってしまいがちですが、自分にフィットしない企業に入社すると苦労するのは目に見えています。
- 幅広い業界を知る
- 志望する業界を絞る
この二つをおこなうために、業界研究は必要なのです。
業界研究の具体的なやり方と手順
就活本を見て「業界研究は大切だ!」と主張していても、「では、一体どうしたらいいの?」というところが不透明なときがあります。そこで、この記事では具体的なやり方と手順をご紹介しましょう。
社会がどのような業界で構成されているか知る(業界分類について)
社会は大きく分けると8つの業界に分けられるといいます。
- メーカー:ものをつくる
- 小売:ものを売る
- サービス:形のないものを売る
- ソフトウェア・通信:情報に関するものを売る
- 商社:ものを動かして利益を得る
- 金融:お金を動かして利益を得る
- マスコミ:情報を広めて利益を得る
- 官公庁・公社・団体:国と地方公共団体の役所
メーカーと一言でいっても、食品や建設、自動車など多くの種類があるので、まずは「多くの業界があるんだな」ということを知りましょう。
とりわけ、BtoB企業(法人を対象にした事業をおこなっている企業)は、普段の生活だと実態が見えにくい傾向があるので、よく調べてみることをおすすめします。
興味がある企業の業界分類がどこに当てはまるか調べる
社会がどのような業界で構成されているか知ったら、どこに興味を持つか、自分の心に敏感になってみましょう。「あっ、おもしろそう!」「へぇ~、もっと詳しく知りたい!」といった知的好奇心が動く業界を見つけるのです。
それは、大学の研究につながる業界かもしれませんし、未知の世界かもしれません。今まで触れたことのない知識でも、「おもしろそう」と思ったら、業界研究を掘り下げてみましょう。
- ・市場規模
- ・ビジネスモデル
- ・売上高
- ・利益率
- ・成長率
- ・業界動向
- ・市場推移
- ・トピック
これらを押さえると良いです。どこの業界に興味があるか明確になったら、企業選びがずいぶんおこないやすくなります。
企業から業界の全体像に視点を広げる
「前から興味があったんだよな」という企業があるなら、どこの業界に所属するか調べて、その業界内での立ち位置をチェックしてみましょう。シェアNo.1であったり、老舗だったりするかもしれません。
業界内での立ち位置をチェックするときに、自然と競合他社の情報を知るので、業界の全体像に視野を広げると良いでしょう。競合他社と比較した上で「やはりこの企業が一番だ」という根拠を明確にできると、志望動機を書きやすいです。その企業の良いところ探しをしていっても良いですね。
他の業界とのつながり・違いを調べる(志望業界の特徴を知る)
さらに、社会は密接に関わっているので、業界同士のつながりを意識しましょう。例えば、メーカー(ものをつくる)と小売(ものを売る)は接することが多いですし、同じ“もの”に携わる仕事です。
違う業界が見えてくると、そちらにも興味が出てくるかもしれません。つながりや違いを知って、「本当にこの志望業界が自分にとって最適か?」ということを確認しましょう。
興味のある企業の業界内での立ち位置を知る
興味のある企業が業界内でどんな立ち位置にあるか知ると、自分のしたいことが明確になるかもしれません。それぞれの企業には強みや特徴があるので、その強みや特徴に共感できるか確かめるのです。
人によっては、企業の求める人物像に無理やり自分を当てはめようとすることがあるでしょう。しかし、どうしても無理が生じてしまうので、負荷がかかります。企業の立ち位置(強み)と自分の強みが合致するところを探っていきましょう。
業界研究をおこなう際にチェックすべきポイント
業界研究をおこなう際にチェックすべきポイントをご紹介します。未来の自分が活躍する姿を想像してみましょう。
今後の成長が期待できる分野かどうか
業界の利益推移から、今後の成長が期待できる分野かチェックするのは重要なことです。あえて、この先が暗い分野に飛び込む必要はないでしょう。ただし、どんなに落ち込んでいる分野でも、ナンバーワンになれば企業として成り立つことが多いです。その企業にはナンバーワンを目指す土壌があるか、という視点も持つと良いでしょう。
思い描くキャリアに近しい人が業界内にいるか(活躍しているか)
思い描くキャリアに近しい人が業界内で活躍しているかチェックするのも大切です。例えば、女性だとまだまだ進出しきっていない分野があります。その分野の先駆者になる覚悟があるのなら良いですが、なかなかいばらの道ではあるでしょう。
業界の雑誌を読んだりネット検索をしたりすると、理想とするビジネスパーソンのイメージは抱けるかと思います。3年後、5年後、10年後、こうなっていたいという具体的イメージを築きましょう。
業界研究に役立つ情報が得られるサイト・ツール・場所
さて、実際の業界研究のやり方をお伝えします。役に立つ情報が得られるツールや場所はこちらの通りです。
就活サイト
大手でいうと「リクナビ」や「マイナビ」などの就活サイトを使うのが有効です。業界の特徴や動向などが分かりやすく書かれています。スマホがあれば、無料で検索できるので大変おすすめできます。
この就活サイトで、企業の平均年齢や平均勤続年数などをチェックしておくと雰囲気が伝わってくるかと思います。興味のある業界や企業だけでもブックマークしてみませんか。
業界団体のHP
業界団体のホームページも要チェックです。「○○業界協会」や「○○業界団体」といった各業界の企業が加盟している任意の団体ホームページではさまざまなコンテンツが楽しめます。
具体的には、「JAMA (一般社団法人 日本自動車工業会)」や「一般社団法人 日本新聞協会」などがあるので、興味があるならチェックしてみましょう。最新のニュースをキャッチできるかもしれません。
書籍
「〇〇業界をまるっと解説」というような本も就活の時期には大変人気です。本屋に行ってみると、何冊か置いてあるのでぺらぺら読んでみると良いでしょう。各業界の動向や特色に加えて、その業界で働く場合の具体的な職種についても解説されています。
節約のために中古本を選んでも良いですが、業界の動向を正確にキャッチするために、発行年はきちんと確認しましょう。
また、「〇〇業界にいた私が本音で語る」というような暴露本はあくまでもその人本人の主張ということを意識しておきましょう。どのように情報を整理するかは、自分自身に委ねられます。
新聞・ニュース
新聞やニュースを定期的にチェックしてタイムリーな情報を手に入れるのも大切です。一人暮らしの学生だと新聞をとっておらず、テレビもないという人がいるようですが、スマホやパソコンで新聞社が配信しているネットニュースを読んだりテレビを視聴したりすることはできます。
この情報化社会では、さまざまな情報が得られるので、いろんなデバイスを活用してみてください。
セミナーや合同説明会
学内で開催されるセミナーや合同説明会などで、業界研究を深めることができます。社員や講師から現場の声を生で聞けるので説得力があるでしょう。無料で参加できるので、積極的に出席してみてはいかがでしょうか。
学校で業界研究のセミナーが開催されないのなら、リクナビやマイナビといった就活サイトを活用してみましょう。
まとめ
「業界研究をどうしたらいいのか、そのやり方が分からない…」という就活生が多くいます。
実際のところ、自己流でやっている先輩も多くいて、これといった正解はないのですが、今回ご紹介した、就活サイトや業界団体のHP、書籍などで情報は集められます。
8つにカテゴライズできる業界のどこが良いのか、明確な軸を持ちましょう。
視野を広げたり絞ったり、試行錯誤する中で見えてくるものがあるでしょう。
転職・人材業界に深く関わるディレクターが『今の職場に不満があり、転職を考え始めた方』や『転職活動の進め方がわからない方』へ、最高の転職を実現できる情報提供を目指している。
本記事はキャリズムを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※キャリズムに掲載される記事は転職エージェントが執筆したものではありません。
- 新着コラム
- 人気コラム
- おすすめコラム