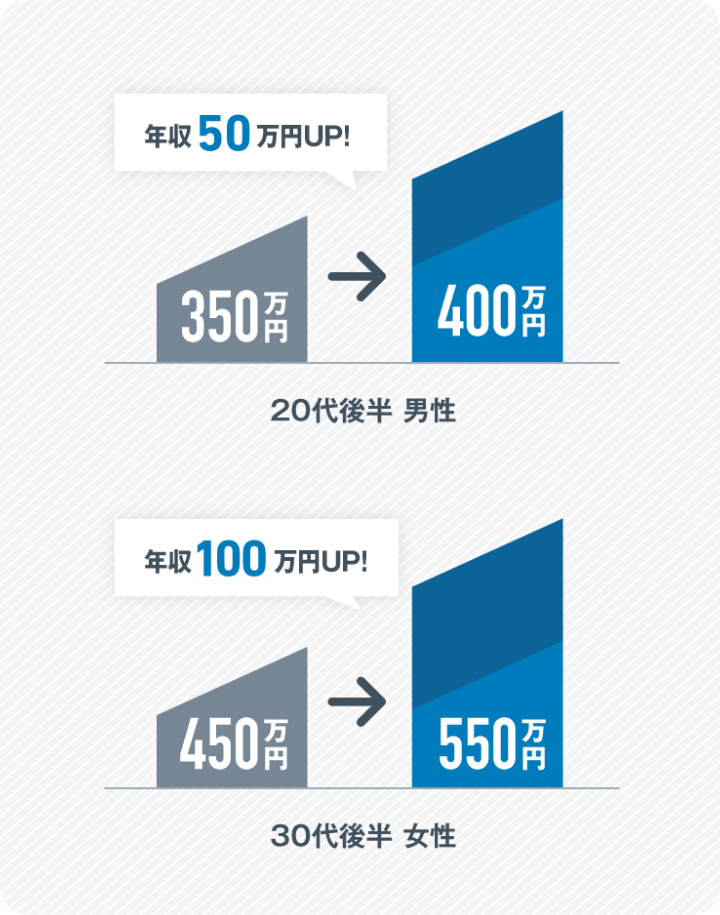そもそも第二新卒(だいにしんそつ)と呼ばれる方々とは、「新卒で入社した3年未満の求職者」を指すのが一般的です。
ですので、「 第二新卒がいつまでの人か?」という疑問に対する答えとして、下記のパターンで言い換えができるものと思われます。
- 4年制大学卒業までなら: 25~26歳ぐらいまで
- 大学院卒業までなら:27~28歳ぐらいまで
「新卒で入社した3年未満の求職者」という認識は概ね一緒ですが、じつは厚生労働省では大人新卒の定義を明確に定めています。
ここでの「第二新卒者」とは、それぞれの企業の中で第二新卒の定義がある場合にはその定義によるものとし、特に定義がない場合は、学校(高校、専門学校、短大、高専、大学、大学院)卒業後、おおむね3年以内の者とした(学校卒業後すぐに就職する新卒者は除く。また、職務経験の有無は問わない)。
引用元: 厚生労働省|若年者雇用を取り巻く現状
ただ、第二新卒の定義も企業によってもさまざまですので、一概に「第二新卒は25,6歳ぐらいまでの人」とは言えないでしょう。
とはいえ、共通して言えるのは「第二新卒」は転職市場では貴重な戦力として考えられているという点です。
そこで、第二新卒と呼ばれる時期や年齢などはいつまでのことを指すのか、わかりやすく解説。
第二新卒は新卒や既卒と違い、転職なども有利に働くタイミングだと言われていますが、どうして転職に有利なのかも解説します。
第二新卒の定義|20代向けの転職サイトで微妙に違う第二新卒の考え方
第二新卒の定義は企業や就職・転職サイトを運営する企業にとっても様々です。まずは企業によってことなる定義を確認しておきましょう。
マイナビ転職の定義
年齢で言えば、4年制大学卒業から考えると25~26歳ぐらいまでになりますが、第二新卒を募集する企業によっても定義が異なるため一概には言えません。マイナビ転職上では、学校を卒業後3年以内の人材を指しています。
引用元:マイナビ転職
まずは人材業界大手のマイナビでは、第二新卒のことを「学校を卒業後3年以内の人材 」と位置付けています。
高校も含めるのかはアンニュイな感じですが、4年生大学卒業から考えると、としていることからか考えると、大学卒業をスタートラインにしていることが伺えます。
マイナビジョブス20’sの場合
マイナビが運営する第二新卒特化型のサービスにおいては、下記のように定義づけています。
第二新卒とは?
学校を卒業後1~3年で、転職または就職を志す若年の方々(25歳前後)
※マイナビジョブ20'sは、派遣社員、契約社員として社会人経験のある方や、留学などの何かしらの理由で、遅れて就職活動を始める方も、第二新卒と定義しています。
引用元: マイナビジョブス20’s
25歳前後の社会人と一応に定義しながらも、大学卒業に限らず、派遣社員などを含めた幅広い方を「第二新卒」としています。こういった定義付けをしているサービスには、多くの求人情報が集まりそうなきがしますね。
リクルートの場合
※第二新卒は「最終学歴を修了後、社会人経験3年目までの若手社会人」と定義しています。
引用元: リクルートホールディングス
最終学歴を「修了」としていることから、リクルートでも大学卒業から換算した方を第二新卒と呼んでいるようです。
第二新卒と既卒との違いは?

社会人経験があるかないか
「既卒」も「第二新卒」と同様に、学校を卒業してから1~3年程度の時期までの人と言われておりますが、高校や大学などを卒業後、一度も社会人経験がないがない人のことを総じて「既卒」と呼ぶ傾向にあります。
2008年ごろのリーマンショック以降、「既卒」になることを避け、あえて留年することで次年度に新卒として就職活動を始める方が増えてきましたが、そうした背景を鑑みた経団連が新しくつくった制度が「第二新卒」と呼ばれるようになったという意見もあります。
既卒に関しても明確な定義はありませんが、社会人経験の有無が大きな違いとして捉えられています。
第二新卒はどのぐらいいるのか?
厚生労働省のデータによると、大学を卒業した人のうち31.9%が新卒で入社した会社から離職しています。
この人達の中で正社員としての雇用を諦めなかった人+前年までの第二新卒で転職活動を続けている者が、おおよそ1年あたりの第二新卒の数になります。
※平成26年は入社二年目での離職率、27年は1年目の離職率
半年以内または3年以上は第二新卒ではない?
明確にはなっていませんが、新卒入社から半年程度でやめてしまった方でも「第二新卒」として扱う傾向はあります。
ただ、その場合は「早期離職」などのカテゴリーに含まれ、純粋な1年以上〜3年程度の「第二新卒」と比べると、やや転職には不利な傾向があります。
企業が第二新卒に期待していることは「仕事への意欲」「入社後の成長」「ポテンシャルの高さ」とされていますから、既卒者や早期離職者の場合、その方々と比べると社会人経験の少なさや業務知識、スキル等で不利になるのは予想しやすいものかと思います。
3年以上の中途採用は既卒と一緒
逆に3年以上経過している場合は「第二新卒」ではなく、ある程度のスキルと経験を備えていると思われるので、第二新卒よりも即戦力を期待される採用となり、第二新卒とは違う見方をされるでしょう。
企業も積極採用|第二新卒が転職に有利な理由と求められること
厚生労働省が行なった調査によると、採用選考での重視項目として、「第二新卒」に求めることは
- 1位:熱意・意欲
- 2位:コミュニケーション力
- 3位:協調性
をあげています。
引用元: 厚生労働省|若年者雇用を取り巻く現状
- 既存の企業体質を変えてくれるのではないか
- 理想を抱いて働いてくれるのではないか
- 前職で経験したことを会社で活かせるかもしれない など
企業側が第二新卒に求める一番のものは「ポテンシャル」という名の将来性です。
基本的なビジネススキルがすでに備わっている
第二新卒の強み1つ目は、社会人経験があるということです。勤続年数が短く専門的なスキルは備わっていませんが、社会人としての基本的なスキルは備わっていると考えられます。
新卒者と比較して社会人マナーや研修を受けており、一定のビジネススキルを持っていること。社会経験が浅い分、企業文化の影響が少なく、柔軟性を持っていること。そして、何より能力・スキルの開発など、大きな成長が見込めポテンシャルが高いことが第二新卒の魅力です。
引用元: マイナビエージェント
まだ前職の色に染まりきっていない
就職後数年で離職している第二新卒は前職のカラーに染まり切っておらず、それが強みになります。就業年数が少なかったからといって経験がまったくないということではありません。前職での経験が活かせ、なおかつ転職先の企業に素早く順応できる貴重な人材と言えます。
目標がはっきりしている
転職を決めたのは自分の目標がはっきりしているから、という第二新卒も多く、明確なキャリアプランとビジョンを持っている人材は企業からも求められます。
新卒で入社する時には誰でもまだ右も左も分からない社会人初心者です。「俺はこの業界で働きたいんだ!」という思いで就職したとしても、実際に働いてみると「思っていたのと違うな」と思うこともしばしばあるでしょう。
第二新卒の人が語る「私はこうなりたい」というビジョンには説得力が生まれやすいので、転職活動の際にも有利になります。「就職してみて本当に自分がやりたい仕事が分かった」「自分の能力を活かすために転職を決めた」というように、明確なビジョンを持って転職活動をしていることをアピールしましょう。
第二新卒のデメリットは?
将来性を買われて採用されることの多い第二新卒ですが、社会人の基礎ができていないとかなりがっかりされます。
また、すぐにやめてしまうかもしれないというのは採用面接の際になんとなく気づかれますので、定着しないことを前提に見られていることを念頭に、面接時には見せ方を工夫する必要があります。
『前職ではどのような経験を積んだのか』という質問には、できるだけ明確かつ具体的な回答ができる程度に経験があるのが理想ですが、もしない場合は「やる気」や「人柄」をアピールできるよう、自分の強みがなんなのか、明確にしておくことも重要です。
第二新卒の転職にベストな時期かプロの判断を仰ぎたい場合
「今の職場からそろそろ転職したいけど、はじめての転職だしどうすればいいかな」
確かに、はじめて転職活動する場合、何をしたらいいのかわからないことも多いですよね。
転職活動で悩んでいるという人は転職エージェントを活用するのがおすすめです。
転職エージェントとは人材紹介サービスの一つです。利用者一人ひとりに担当スタッフがつき、転職相談に乗ってくれる他、企業の求人紹介や面接のセッティング、内定時の給与交渉も行ってくれます。
転職にかかわる全てのサポートをしてもらえるので、自分一人で転職活動を行うよりもスムーズに転職活動を行うことができるでしょう。
転職エージェントのメリット・デメリット
メリット
- 転職エージェントは無料で利用できる
- 非公開求人に応募できる
- 履歴書や職務経歴書の添削や、面接の練習をしてくれる
- 面接日などを自分の都合に合わせて調整してくれる
- 面接後、志望度が高い場合に企業に自分をアピールしてくれる
転職エージェントは基本的に全てのサービスを無料で受けることができます。というのも、企業の採用業務の一部を転職エージェントが担う代わりに、報酬を企業から受け取っているからです。また、転職エージェントでは通常の転職サイトでは公開されない、数多くの非公開求人を取り扱っています。
企業が求人を非公開にする理由はさまざまですが、決して条件が悪いわけではなく、中には優良企業や条件がよい求人もあるため、積極的にチェックしておきたいですね。
その他にも、履歴書や職務経歴書の添削や、面接後にエージェントが企業にプッシュしてくれるので、転職活動を有利に運ぶことができます。
デメリット
- 自分の希望している会社を紹介してもらえない可能性がある
- 自分の意思にかかわらず転職を強要される場合がある
転職エージェントは、利用者が紹介した企業に採用されてはじめて報酬を得ることができます。そのため、自分の利益しか考えていないエージェントに当たってしまった場合、希望していない企業への入社を強要してくる可能性があります。
結局、自分のキャリアを決めるのは自分自身です。転職エージェントを利用する際には、信用できるエージェントかどうか自分自身できちんと見極める必要があります。
転職サイトと転職エージェントの違い
転職を考えている人の中には転職サイトに登録している人もいるでしょう。その際、「転職サイトと転職エージェントってどう違うの?」と疑問に思うかもしれません。
転職サイトでの求人活動は、能動的に自ら転職活動を行われければなりません。
企業への応募から、履歴書の作成、面接日の調整まで全て自分で行う必要があります。そのため、仕事をしながら転職活動をする場合、内定獲得までに思った以上に時間がかかるかもしれません。
対して、転職エージェントは求人の応募から内定獲得、入社に至るまで転職活動の全てのフェーズでサポートを受けることができます。
効率よく転職活動をしたい、絶対に転職したいという人は転職エージェントを活用することをおすすめします。
第二新卒で成功ポイント|「いつまで」その会社で働くのか期限を決めておく
もしあなたが新卒入社でまだ1年程度であるならば、第二新卒の枠は難しいでしょう。
新卒では狙えなかった企業があるなら、「再挑戦したい」と思う場合も多いとは思います。
ただ、人よりも突出する強みがなければ転職はそう簡単にはいきません。転職への理想が高すぎる場合も同じです。大手企業への転職をしたい方も多いかと思いますが、視野を広げて考えてみることで、内定獲得に近づく可能性が高いです。
企業は第二新卒をいつでも求めています。一度社会人をちゃんと経験し、ある程度の経験を積んだ第二新卒として応募するほうが理想の転職も実現できる可能性が高まります。
|
転職に失敗する第二新卒の特徴 |
|
入社後数ヶ月以内に退職してしまっては、面接で不利になる可能性の方が高いですから、「いつまで働くか期限を決めて」「第一志望に転職するための下積みをする」ぐらいでいることも大事です。
転職・人材業界に深く関わるディレクターが『今の職場に不満があり、転職を考え始めた方』や『転職活動の進め方がわからない方』へ、最高の転職を実現できる情報提供を目指している。
本記事はキャリズムを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※キャリズムに掲載される記事は転職エージェントが執筆したものではありません。
- 新着コラム
- 人気コラム
- おすすめコラム