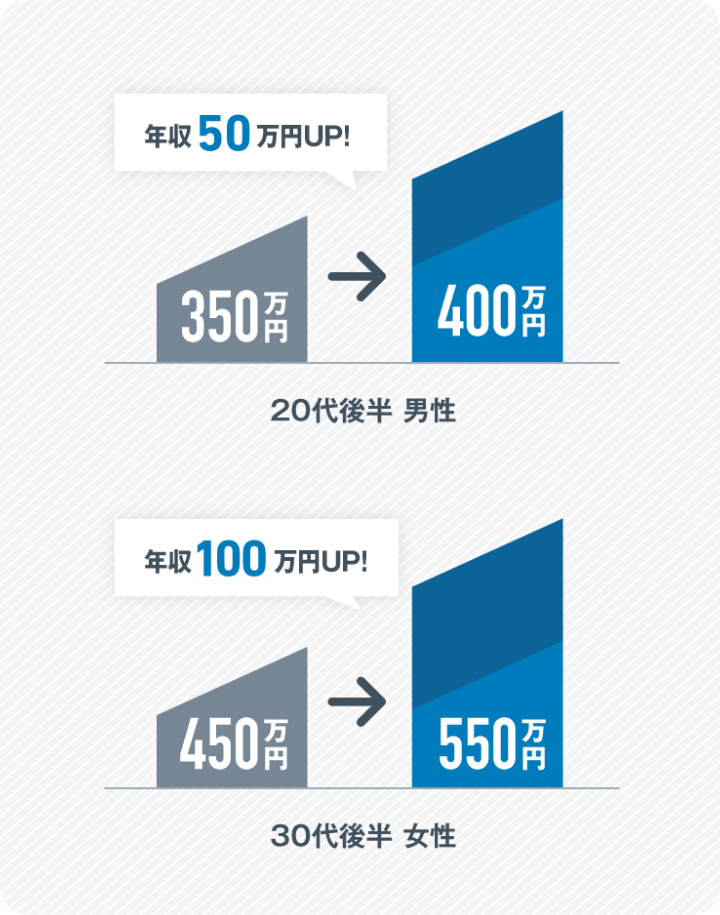「弁護士になりたいけれど、理系在籍・出身でも大丈夫なのかな?」
文理選択で理系を選んでしまった後に、文系向けの仕事に就くのは難しそうだなと感じますよね。
中でも、文系向け職種で最上位に属する「弁護士」は、理系から目指すのは無理だと思うかもしれません。
結論を言うと、理系でも弁護士になるのは可能です。司法試験にさえ受かってしまえば、出身学部に関係なく、弁護士になれます。
もちろん、司法試験に合格できたとしても、働ける場所がなければ、資格を取得しても意味ないですよね。
弁護士の多くが文系という中、理系出身であるのは強みであり、実際ニーズもあります。
というのも、法律問題の中には、文系の知識・感覚だけでは対処が難しい事案(例えば、知的財産、IT分野、医療関係など)も少なくないからです。
では、理系から弁護士を目指すにはどうすればよいのでしょうか。
この記事では、理系出身者が弁護士になる方法や主な就職先、司法試験の勉強方法などについて解説します。
理系の大学や学部出身でも弁護士にはなれる?
冒頭でもお伝えした通り、理系大学・学部出身であっても弁護士になることは可能です。
原則、弁護士となるには司法試験に合格しなくてはなりません。
しかし、医師国家試験のように医学部でないと受験できないわけではなく、法学部以外の方でも受験資格さえ満たしていれば、試験を受けられます。
そのため、理系出身者であっても、司法試験にさえ合格できれば、弁護士になれるわけです。
理系出身者が弁護士を目指す際の手段と流れ
理系出身者が弁護士を目指す場合、以下のような手段と流れで進んでいきます。
- 司法試験の受験資格を手に入れる
- 司法試験に合格する
- 司法修習を終了する
- 二回試験に合格する
それぞれ確認していきましょう。
司法試験の受験資格を手に入れる
司法試験は、法学部以外の方でも受験可能ではあるものの、誰でも受けられるわけではありません。
- 法科大学院を卒業する
- 予備試験に合格する
司法試験を受けるには、上記のうち、どちらかを満たしている必要があります。
法科大学院を卒業する
弁護士含めた法曹となるための基本的なルートは、法科大学院を卒業した上で、司法試験に合格する方法です。
法科大学院とは、質の高い法曹を養成するのを目的に創設された専門職大学院で、アメリカのロースクール制度をモデルとしています。
法科大学院には、法学未修者を対象とした3年コースと、既修者対象の2年コースがあります。
法学部出身でなければ、未修者コースに入学するのが一般的です。ですが、法学部でないと受験できないわけではなく、既修者向けの試験に合格すれば入学できます。
なお、以前は法科大学院の入学試験を受けるためには、「法科大学院全国統一適性試験」の受験が必要でした。
しかし、入試を行う法科大学院の減少により、現在は実施されていません。
法科大学院を卒業すれば、司法試験の受験資格を取得できますが、後述する予備試験に比べると、費用と時間がかかるというデメリットがあります。
予備試験に合格する
司法試験の受験資格は、予備試験に合格することでも取得できます。
予備試験とは、合格者に司法試験の受験資格を与えるために行われる試験で、誰でも受験することができます。
本来であれば、法科大学院を卒業しないと受験資格は得られません。
ただ、受験資格を制限してしまうと、経済的理由等により法科大学院に通えない人は司法試験を受けることができなくなります。
そうした事情を理由に、優秀な人材が司法試験の受験を断念してしまうのはもったいないため、一種の救済措置として予備試験が行われているのです。
法科大学院を卒業しなくても司法試験を受けられるのなら、みんな予備試験を利用するのではと思うかもしれませんが、その合格率は5%未満。
合格率でいうと、司法試験よりもだいぶ低いため、素直に法科大学院を卒業して、受験資格を取得するほうが簡単なのです。
ただ、予備試験の合格は簡単ではないものの、合格者の司法試験合格率は7割程度。
【予備試験合格者の司法試験受験状況】
|
実施年度 |
受験者 |
合格者 |
合格率 |
|
2014年 |
244人 |
163人 |
66.8% |
|
2015年 |
301人 |
186人 |
61.8% |
|
2016年 |
382人 |
235人 |
61.5% |
|
2017年 |
400人 |
290人 |
72.5% |
|
2018年 |
433人 |
336人 |
77.6% |
予備試験を突破できる学力があれば、司法試験本番でも合格できる可能性は高いといえます。
司法試験に合格する
予備試験の合格にしても、法科大学院の卒業にしても、あくまでスタートラインに立っただけです。
司法試験という最大の難関を突破しない限り、弁護士資格の取得はありえません。
司法試験は例年5月に行われています。4日間に及ぶ長丁場の試験で、最初の3日間は論文式試験。公法系・民事系・刑事系・選択科目の4分野から事例問題が出題されます。
最終日は短答式試験。マークシート方式で憲法・刑法・民法の3分野が出題されます。
合格発表は例年9月です。合否判定は論文式・短答式両方を総合して行われます。ただし、短答式試験の結果が基準に満たない場合は、その時点で不合格です。
なお、司法試験を受験するに当たり、28,000円の受験手数料がかかる点には注意してください。
1年間の司法修習を経る
司法試験に合格しても、実はまだゴールではありません。弁護士となるためには、1年間の司法修習を受ける必要があります。
司法修習とは、裁判所法で定められた法曹教育制度。法律実務に関する知識・実技や、高い職業意識、倫理観を養うために実施されています。
法曹になるためには必須の課程であり、裁判官,検察官,弁護士いずれの道を選ぶにしても、同一にカリキュラムによって行われます。
司法修習生考試(二回試験)に合格する
司法修習の最後には、司法修習生考試いわゆる二回試験が待ちうけます。この試験に合格すると、晴れて弁護士となることができます。
二回試験ではほとんどの修習生が合格するため、簡単そうに思えますが、実はかなり大変な試験です。
試験科目は、民事裁判、刑事裁判、検察、民事弁護、刑事弁護の5科目。1日1科目ずつ、連続して5日間試験を実施します。
1日1科目なら楽勝と思うかもしれないですが、なんと試験時間は昼食時間含めて7時間半です。
体力的な厳しさはもちろん、二回試験に落ちたら法曹資格が取得できないプレッシャーも影響して、少なからず不合格者が出ています。
救済措置はないため、試験に落ちた場合は翌年の二回試験まで待たなくてはなりません。
理系出身者が司法試験に合格するには
理系出身で、いままで法学の勉強したことがない場合、どうやって試験勉強すればよいかわからない方も多いかと思います。
選択肢として考えられるのは、おそらく以下の3つ。
- 独学で勉強する
- 予備校に通う
- 法科大学院に通う
独学で司法試験に合格できれば、かかる費用は最も少ないでしょうが、あまり現実的ではありません。
合格する確率を最大限上げたいのであれば、3つすべて行うことです。法科大学院を卒業できれば、予備試験の勉強は必要ありません。
法科大学院で法律の基礎知識を学びつつ、予備校で司法試験に合格するための知識・ノウハウを身につけ、独学でも勉強するのがベストでしょう。
もちろん、金銭的・時間的に厳しいのであれば、予備校と法科大学院のどちらかを選ぶしかありません。
短期間かつ働きながらであれば、予備校の通信講座を利用するとよいでしょう。合格に2,3年費やすことも覚悟しているなら、法科大学院で勉強するもありです。
どの選択肢を選ぶにせよ、質と量の両方が確保できる勉強方法でなければ、司法試験合格は難しいでしょう。
理系弁護士の主な就職先

司法試験を合格したからには、特定の分野に関わらず活躍することは可能ですが、理系の知識や考え方が活かせる分野が好まれる傾向になります。
具体的には、以下に挙げるような法律問題を扱う事務所だと、理系弁護士のニーズは高いといえるでしょう。
- 知的財産に関する問題を扱う事務所
- 医療問題を扱う事務所
- 建築関係の問題を扱う事務所
- IT企業のインハウスロイヤー など
やはり、知的財産や医療、建築など、理系分野の中でも特に高度な専門知識が求められる分野では、文系出身よりも理系出身の弁護士が強いといえます
理系の素養がないと、正しく問題点を理解することが難しく、適切な対処ができないリスクが高まります。
文系出身の弁護士が多いからこそ、理系であることを活かせる事務所で働けば、独自のポジションを築けるでしょう。
弁理士やパラリーガルになるという選択肢もある
理系だけど、法律に関わる仕事をしたいという場合、必ずしも弁護士にこだわる必要があるとは限りません。
例えば、理系出身であれば「弁理士」という選択肢も考えられます。
弁理士とは、知的財産に関する専門家であり、弁護士と同じく国家資格の一つ。
主な業務は、特許権、実用新案権、意匠権など、知的財産権を取得する際に必要な手続きを代理することです。
知財に関するトラブルの相談や、権利取得に際して助言やコンサルティングなどの業務も行います。
弁理士試験合格者の7割が理工系学部であることから、法律関係の仕事をしたい理系出身者にはうってつけの資格かもしれません。
また、法律事務所で働きたいのであれば、パラリーガルという選択肢もあります。
パラリーガルとは、法律事務所で働く弁護士の業務をサポートする職員のこと。
事務的な作業に加え、法律の知識に基づいて行う業務も担うことから、高度な専門性も求められる仕事です。
とはいえ、事務職や秘書に近い扱いであるため、年収が低めなのがネックといえます。
まとめ
弁護士は理系・文系に関わらず、司法試験に合格し、司法修習を修了すれば、誰でもなることはできます。
ただし、司法試験を受けるためには、受験資格を満たしてなくてはなりません。
司法試験の受験資格を満たす条件は2つ。
- 法科大学院を卒業する
- 予備試験に合格する
法科大学院を卒業するほうが条件的にはゆるいものの、費用と時間がかかります。
他方、予備試験は費用面と時間面の負担は少ないですが、司法試験本試験以上に合格率が低い難関試験です。
司法試験に合格しても、すぐ弁護士資格が取得できるわけではありません。1年間司法修習に従事した後、二回試験に合格する必要があります。
理系出身であることを活かして弁護士活動をするのであれば、理系知識が役立つ法律問題を扱う事務所に就職するとよいでしょう。
具体的には、以下のような事務所が挙げられます。
- 知的財産に関する問題を扱う事務所
- 医療問題を扱う事務所
- 建築関係の問題を扱う事務所
- IT企業のインハウスロイヤー など
また、法律問題を扱う職種は、弁護士だけに限りません。
弁理士やパラリーガルなど、その他の選択肢もあるので、弁護士にこだわりがなければ、さまざまな職種を検討してみるとよいでしょう。
転職・人材業界に深く関わるディレクターが『今の職場に不満があり、転職を考え始めた方』や『転職活動の進め方がわからない方』へ、最高の転職を実現できる情報提供を目指している。
本記事はキャリズムを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※キャリズムに掲載される記事は転職エージェントが執筆したものではありません。
- 新着コラム
- 人気コラム
- おすすめコラム