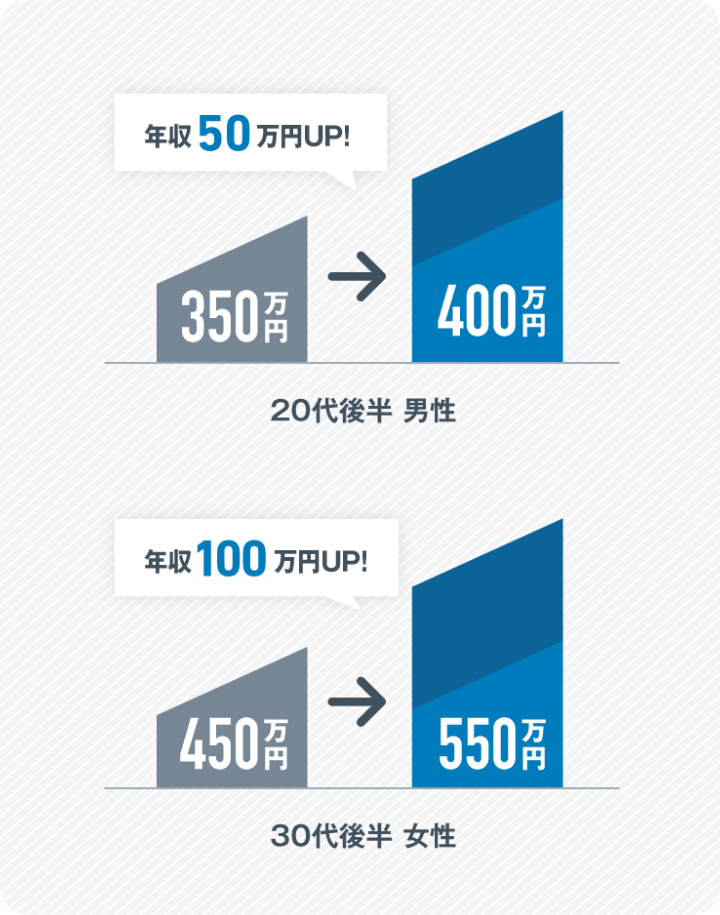最近では「国際弁護士」という名称に、聞き馴染みがある方も増えたのではないでしょうか。
TVで活躍中の八代英輝弁護士が名乗られていますし、小室圭さんが留学される際にも話題になりました。
しかし、「国際弁護士」という名称は世間に広まったものの、具体的にどういった仕事をしているのかわからないですよね。
何となく海外で仕事をしていそうなイメージがあって、年収を結構もらっていそうといったところでしょうか。
この記事では、国際弁護士とは、どのような弁護士を指すのか、業務内容や年収なども含めて詳しく解説します。
また後半では、国際弁護士になる方法や注意点についても解説しますので、参考にしてみてください。
国際弁護士とは
そもそもですが、国際弁護士についての資格や定義はなく、あくまでそのような肩書で活動されている方がいるだけです。
大体、国際弁護士と名乗っている方は、以下の3パターンで分類することができます。
- 日本と海外両方の弁護士資格を持っている
- 日本の弁護士資格を持っていて外国の案件を扱っている
- 海外の弁護士資格だけを持っている
それぞれ確認していきましょう。
日本と海外両方の弁護士資格を持っている
一般的な方が国際弁護士と聞いて、イメージするのは「日本と海外両方の弁護士資格を持っている」パターンかと思います。
日本の弁護士資格により認められているのは、国内での活動のみです。海外で弁護士活動をするためには、その国でも弁護士資格を取得しなければなりません。
前述した八代英輝弁護士は、このパターンに該当します。
日本の弁護士資格を持っていて外国の案件を扱っている
いわゆる渉外弁護士がこのパターンに当たります。
「渉外」とは、外国と交渉することを意味し、その言葉通り、外国が関わるビジネス法務案件を主に扱う弁護士のことです。
渉外弁護士の多くは、渉外事務所で働いており、中でも有名なのが五大法律事務所です。
- 西村あさひ法律事務所
- 長島・大野・常松法律事務所
- アンダーソン・毛利・友常法律事務所
- TMI総合法律事務所
- 森・濱田松本法律事務所
なお、ビジネス法務以外の外国が関わる案件(例:国際離婚や在留資格の手続きなど)を扱う弁護士のことは、通常、渉外弁護士とは呼びません。
海外の弁護士資格だけを持っている
海外の弁護士資格しか持っていない方も一定数います。この場合、原則として日本国内で弁護士活動をすることはできません。
ただし、例外として外国法事務弁護士に登録すると、日本国内において、弁護士資格を保有する国の法律事務のみ扱うことが可能となります。
あくまで、資格を持つ国の法律事務を日本国内で扱うことが認められるだけで、日本の弁護士と同じように活動できるわけではありません。
外国法事務弁護士の登録数は、2021年4月1日時点で448名となっています。
国際弁護士の年収はどのくらい?

国際弁護士の年収に関する統計やデータも存在しませんが、少なくとも1,000万円は超えると思ってよいでしょう。
例えば、渉外事務所勤務の弁護士は、基本的に年収が高く、20代で1,000万円の大台を突破している方も少なくありません。
五大法律事務所のような大手渉外事務所でパートナー弁護士になると、1億を超える年収がもらえるようです。
【五大法律事務所の年収例】
|
事務所名 |
最低年収 |
最高年収 |
|
西村あさひ法律事務所 |
1,000万円 |
2,450万円 |
|
長島・大野・常松法律事務所 |
1,800万円 |
2,500万円 |
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 |
1,100万円 |
2,600万円 |
|
TMI総合法律事務所 |
800万円 |
1,000万円 |
|
森・濱田松本法律事務所 |
1,200万円 |
2,400万円 |
参考:Openwork
また、外資系法律事務所の年収も高め年収が1,000万円以上となるケースも少なくありません。
|
事務所名 |
最低年収 |
最高年収 |
|
ジョーンズ・デイ法律事務所 |
1,000万円 |
1,000万円 |
|
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ |
1,200万円 |
1億2,000万円 |
|
ホーガン・ロヴェルズ法律事務所 |
1,100万円 |
1,100万円 |
参考:Openwork
もちろん、国際弁護士であっても扱う分野によっては、年収1,000万円に届かないことも十分考えられます。
ですが、企業法務を中心に扱う国際弁護士であれば。年収が1,000万円を超える可能性は高いといえるでしょう。
国際弁護士の業務内容
国際弁護士だからといって、なにか特殊な業務を行うわけではありません。
取り扱う分野に応じた業務を担うことになります。
例えば、外資系法律事務所や渉外事務所勤務の場合、主にビジネス法務系の案件を扱うことが多いでしょう。
企業がM&Aや融資を行う際に法的アドバイスや契約書のレビューなど、クライアントのニーズに応じて幅広く対応しています。
場合によっては、一般民事を含め紛争事件を担うこともあるでしょう。
国際弁護士になる方法

国際弁護士になるには、以下3つの方法が考えられます。
- 海外の弁護士資格をとる
- 渉外案件を扱う事務所に転職
- インハウスロイヤー
それぞれ確認していきましょう。
海外の弁護士資格をとる
日本以外の国で法律事務を扱いたいのであれば、現地の弁護士資格を取得しなければなりません。
例えば、アメリカで弁護士資格を取得するには、日本と同様にロースクールを卒業後、州ごとに行われる司法試験で合格する必要があります。
なお、アメリカのロースクールの場合、日本で法学部や法科大学院を卒業、弁護士資格を持っている人であれば、1年コース(LL.M)の利用が可能です。
仮に海外の弁護士資格を取得できたとしても、現地で仕事を得ることは簡単ではないでしょう。
渉外案件を扱う事務所に転職
海外で働くというより、国際的な案件を扱うことに興味があるのであれば、渉外事務所や外資系法律事務所への転職がおすすめです。
渉外事務所や外資系法律事務所であれば、日本にいながら海外の案件を扱うことができます。
ただ、必ずしも渉外案件の担当になれるとは限らないので注意してください。
また、日本で働くとはいえ、渉外案件を扱うのであれば語学力が求められます。
インハウスロイヤー
海外と取引がある企業にインハウスロイヤーとして、入社するのも選択肢の一つです。
近年では、M&Aを積極的に行う企業も多く、またコンプライアンスに対する意識も高まりを見せています。
そうした中で、社内に法律の専門家を常駐させておきたいと、考える企業も増えてきているようです。
ニーズが高まっていることから、インハウスロイヤーに対する待遇も比較的よく、年収1,000万円以上の求人も少なくありません。
国際弁護士に関する注意点
国際弁護士の肩書は、名乗ろうと思えば、海外の弁護士資格をもってない・渉外案件の経験がないという人でも名乗ることができます。
そのため、下手に自分の肩書として利用すると、信用を下げてしまうかもしれません。
また、国際弁護士=渉外事務所勤務を指すかと思いますが、渉外弁護士の仕事はかなりの激務です。
連日深夜まで働き、休日も出勤という働き方をしている渉外弁護士も少なくありません。
高収入だけにつられてしまうと、痛い目を見るでしょう。
まとめ
実は国際弁護士という資格はなく、明確な定義もないことに驚かれた方は多いかもしれません。
定義や資格はありませんが、国際弁護士を名乗っている方は、以下のいずれかの場合です。
- 日本と海外両方の弁護士資格を持っている
- 日本の弁護士資格を持っていて外国の案件を扱っている
- 海外の弁護士資格だけを持っている
おそらく一般の方がイメージする国際弁護士に近いのは、外国が関わるビジネス法務案件を主に扱う「渉外弁護士」ではないかと思います。
初任給から年収が1,000万円を超えるなど、華々しいイメージの渉外弁護士ですが、実はかなりの激務。
もちろん、国際的な案件を扱うため、成長の機会も多いですが、生半可な気持ちでは務まらないでしょう。
それでも、国際弁護士になりたいという方には、以下の方法が考えられます。
- 海外の弁護士資格をとる
- 渉外案件を扱う事務所に転職
- インハウスロイヤー
渉外事務所やインハウスロイヤーへの転職を考えているのであれば、転職エージェントの利用がおすすめです。
中でも、MS-Agentは士業の転職に特化したサービスを提供しており、さまざまな渉外弁護士や企業の求人が見つけられるでしょう。
転職・人材業界に深く関わるディレクターが『今の職場に不満があり、転職を考え始めた方』や『転職活動の進め方がわからない方』へ、最高の転職を実現できる情報提供を目指している。
本記事はキャリズムを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※キャリズムに掲載される記事は転職エージェントが執筆したものではありません。
- 新着コラム
- 人気コラム
- おすすめコラム